|
アップ履歴
2020年3月23日 ひるねスイーツ1.40.3
マイ・ブックサーフィン
『パラダイム・ブック』
◎3ステップス哲学
→3ステップス自然哲学
『旅人』
◎※例えば、“天動説”が多くの人に信じられていたかどうかよりも、“天動説”が自然(nature)と調和しているかどうかこそが重要なのだと思います。
→※“天動説”や“地動説”を含む何かの説が多くの人に信じられていたかどうかよりも、“天動説”や“地動説”を含む何かの説が自然(nature)と調和しているかどうかこそが重要であるのと同様だと思います。
◎尊重され続けるだと思います。
→尊重され続けるのだと思います。
◎※なお、後に、3ステップス理論(3Steps Theory)の表記を3ステップス哲学(3Steps Philosophy)と変更しましたので、一般3ステップス哲学(General Philosophy of 3Steps)を探究する旅が本格化したことになります。
→※なお、後に、3ステップス理論(3Steps Theory)の表記を3ステップス自然哲学(3Steps Philosophy of Nature)と変更しましたので、一般3ステップス自然哲学(General 3Steps Philosophy of Nature)を探究する旅が本格化したことになります。
◎該当部分(一般3ステップス哲学の前身)→(一般3ステップス自然哲学の前々身)
『3年 全国大学 国語入試問題詳解』
◎※こういった筆者が、「『7つのパラダイム』【物語3.08】」のような作品を育てているのですから、
→※こういった筆者が、「『7つのパラダイム』【物語】」のような作品を育てているのですから、
『imidas1992』
◎※「単位や資格をとるための勉強」の合間では── →※「単位や資格をとるための勉強」や気晴らし(写真、音楽…)等々の合間では──
◎該当部分 下さりました。→くださりました。
◎ 余計な下線の削除 ※『複雑系入門』は、→ ※『複雑系入門』は、
『人間性の心理学』
◎『ぐるぐるカーテン』や『Sing Out!』や『私のために 誰かのために』…→『Sing Out!』や『私のために 誰かのために』…
エッセイ
『北の国から89帰郷』
◎追加 しばらく体調崩してスランプに陥っていた時期、全作通して拝見したことがあります。うまく言えませんが、忘れていた大事なものを思い出すことができたり、それまで気づかなかったことに気づくことができたりしたように感じました。やはり、(帰郷89に限らず)『北の国から』は、すべて、(薬のようでもある)奇跡的な作品だと思います。感謝いたしております。
2020年1月13日 ひるねスイーツ1.40.2
マイ・ブックサーフィン
『人間性の心理学』
◎ しかし、アドラー心理学だけにとどまるよりも“アドラー心理学もマズロー心理学も”の方が、よりフルーツフルであると思います。
→ ただし、アドラー心理学だけにとどまるよりも“アドラー心理学もマズロー心理学も”の方が、よりフルーツフルであると思います。
◎あるいは、アドラー自身の説からアドラーの後継者の説へと変化しているせいのかもしれません。
→あるいは、アドラー自身の説からアドラーの後継者の説へと変化しているせいなのかもしれません。
◎マズローにとっての共同体感覚は、自己実現的人間の特徴であり、前提でした
→マズローにとっての(人類に対する)共同体感覚は、自己実現的人間の特徴であり、前提でした
◎
例えば、「(心底やりたいことをやるという意味で)自己中心的でありなががら、同時に、社会貢献をする(みんなを喜ばせようとする)」という人生のあり方も存在しうるのだと思います。
→ 例えば、「(心底やりたいことをやるという意味で)自己中心的でありなががら、同時に、社会貢献をする(みんな(∋不特定の誰か)を喜ばせようとする)」というライフのあり方も存在しうるのだと思います。
◎そして、もう1つの必要条件は、『ぐるぐるカーテン』や『Sing Out!』(乃木坂46)の中にもある「誰かのために」を含む『For』『Out』路線なのだと思います。
→そして、もう1つの必要条件は、『ぐるぐるカーテン』や『Sing Out!』や『私のために 誰かのために』…(乃木坂46)の中にもある「(不特定の)誰かのために」を含む『For』『Out』路線なのだと思います。
◎ ニュートン・フルーツ
→ ニュートンフルーツ
◎※具体的には、例えば、『マズロー本』が、『アドラー本』はもとより、『6秒でストレスがとれる!』『7つの習慣』『目からウロコの文化人類学』『君たちはどう生きるか』… とも何らかの接点(関連部分)があることに気づきました。
→※具体的には、例えば、『マズロー本』が、『アドラー本』はもとより、『6秒でストレスがとれる!』『7つの習慣』『パラダイム・ブック』『旅人』『進化の傷あと』『目からウロコの文化人類学』『君たちはどう生きるか』… とも何らかの接点(関連部分)があることに気づきました。
『進化の傷あと』
◎ 当然、“水辺(特に海辺)生活がヒトを生んだ説”は、“後件肯定”による“大胆な推理”に過ぎません(参考 『論理的に考えること』(マイ・ブックサーフィン『3?N ?S?????w ?????????????????』))。
→ 当然、“水辺(特に海辺)生活がヒトを生んだ説”は、“後件肯定”による“大胆な推理”に過ぎません(参考 『論理的に考えること』(マイ・ブックサーフィン『3年 全国大学 国語入試問題詳解』))。
2019年12月7日 ひるねスイーツ1.40.1
マイ・ブックサーフィン
『人間性の心理学』
◎※以上の文章をまとめたのちに、次の記述に出会いました。
→※以上の文章をすでにまとめ終わっていたのちに、次の記述に出会いました。
◎ しかし、いずれにせよ、「どちらかと言えば、アドラーが『Against』の方向にいるとすれば、マズローが『For』の方向にいる」という印象は、ぬぐえないと思います。
→ しかし、いずれにせよ、どちらかと言えば、アドラーの人生が『Against』の方向にあったとすれば、マズローの人生は『For』の方向にあったようです。
◎※どちらかと言えば、アドラーが主に『Against』↓を目指していたとするなら、マズローは主に『For』↑を目指していたとも言えます。
→※どちらかと言えば、アドラーが主に『Against』↓を目指していたとするなら、マズローは主に『For』↑を目指していたとも要約できます。その意味でも、やはり、どちらかと言えば、アドラーが『Against』の方向にいたとすれば、マズローは『For』の方向にいたことになります。
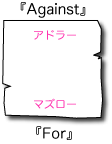
◎該当部分 (=『For』“『In』&『Out』”)→(=For“『In』&『Out』”)
◎該当部分 (=『For』“『In』&『Out』)→(=For“『In』&『Out』”)
◎7番目のパラダイム(3ステップス理論)→7番目のパラダイム( ) )
◎ ※例によって、 一方で、筆者は、例によって、マズローのすべてを鵜呑みにし、すべてにおいて同調しているわけではありませんが──(そのようなことをしたら、やはり自分をなくしてしまうと思います。例えば、マズローが科学を絶対視しすぎていたところ、(部分も全体も大事するのではなく)全体のみを大事にし過ぎているところ、「第四勢力としてのトランスパーソナル心理学」を目指したところは、鵜呑みにできません)。
→※なお、例によって、一方で、筆者は、マズローのすべてを鵜呑みにし、すべてにおいて同調しているわけではありません(そのようなことをしたら、やはり自分をなくしてしまうと思います)。
例えば、マズローが科学を絶対視し過ぎていたところ、(部分も全体も大事するのではなく)全体のみを大事にし過ぎていたところ、(自己実現者が本来『愛他的で、献身的で、自己超越的、社会的である』という経験的事実を伝えることをあきらめて)「第四勢力としてのトランスパーソナル心理学」を育んだところは、鵜呑みにできません。
◎文字サイズの変更
(p.203『完全なる人間』アブラハム・H・マズロー著 上田吉一訳) ※傍点部を太線で示しています。下線は筆者によります。『自己実現の価値は、また実現していなくても、目標として現実に存在する。』の中の『また』を、英原著にもとづき、『まだ』と修正させていただきました。
→ (p.203『完全なる人間』アブラハム・H・マズロー著 上田吉一訳) ※傍点部を太線で示しています。下線は筆者によります。『自己実現の価値は、また実現していなくても、目標として現実に存在する。』の中の『また』を、英原著にもとづき、『まだ』と修正させていただきました。
◎(『量子と実在 不確定性原理からベルの定理へ』(ニック・ハーバート著 はやし・はじめ訳 p.360-361 白揚社)
→(『量子と実在 不確定性原理からベルの定理へ』(ニック・ハーバート著 はやし・はじめ訳 p.360-361 白揚社) 下線は筆者によります。
◎ 「自己実現的人間フルーツのネットワーク」はもとより、ウェブックス (Webooks)の存在にも、心から感謝いたしております。
→
こういったウェブックス(Webooks)のおかげで、このページを含む、木岬さんぽフルーツも育まれております。
心から感謝いたしております。
◎追加
『6秒間でスとレスがとれる!』
ストレーベル 斉藤茂太訳 知的生き方文庫 三笠書房 |
呼吸の状態を含む、体のコンディションを整えることは、マズローの欲求の階層説の生理的欲求と関連していることに気づきました。 |
『7つの習慣』
スティーブン・R・コヴィー キングベアー出版
|
やはり、『7つの習慣』も、自己実現のためにおおいに役立つと思います。なお、アドラーが『Against』の方向なら、スティーブン・R・コヴィーは、『For』の方向にいるとも言えそうです。 |
『目からウロコの文化人類学』
斗鬼正一 ミネルヴァ書房 |
『目からウロコの文化人類学』がきっかけで育まれた「文化がフルーツである」(文化⊂フルーツ)という考えが、自己実現と関連していることに気づきました。 |
◎
『改訂新版 人間性の心理学
モチベーションとパーソナリティー』
(A.H.マズロー著 小口忠彦訳 産業能率大学出版部) |
|
『君たちはどう生きるか?』
(吉野源三郎 ポプラ社 ──冒頭の詩)
|
『アルフレッド・アドラー
人生に革命が起きる100の言葉』
(小倉宏 ダイヤモンド社 |
『アドラー100の言葉』
(監修 和田秀樹 宝島社) |
『嫌われる勇気』
(岸見一郎、古賀史健 ダイヤモンド社) |
『アドラーを読む 共同体感覚の諸相』
(岸見一郎 アルテ)
『人間知の心理学』
(アルフレッド・アドラー 岸見一郎訳 アルテ)
『人生の意味の心理学』
(アルフレッド・アドラー 岸見一郎訳 アルテ)
『子どもの教育』
(A・アドラー 岸見一郎訳 一光社)
… |
『マズローの心理学』
(フランク・ゴーブル著 小口忠彦監訳 |
→
『改訂新版 人間性の心理学
モチベーションとパーソナリティー』
A.H.マズロー著 小口忠彦訳 産業能率大学出版部 |
|
『君たちはどう生きるか?』
吉野源三郎 ポプラポケット文庫 ポプラ社
(冒頭の詩)
|
『アルフレッド・アドラー
人生に革命が起きる100の言葉』
小倉宏 ダイヤモンド社 |
『アドラー100の言葉』
監修 和田秀樹 宝島社 |
『嫌われる勇気』
岸見一郎、古賀史健 ダイヤモンド社 |
『アドラーを読む 共同体感覚の諸相』
岸見一郎 アルテ
『人間知の心理学』
アルフレッド・アドラー 岸見一郎訳 アルテ
『人生の意味の心理学』
アルフレッド・アドラー 岸見一郎訳 アルテ
『子どもの教育』
A・アドラー 岸見一郎訳 一光社
… |
『マズローの心理学』
フランク・ゴーブル著 小口忠彦監訳
産業能率大学出版部 |
『6秒間でストレスがとれる!』
◎ 受験に失敗し、失意の中── 書店内をめぐっていた時だ。
→ 受験に失敗し、失意の中、書店内をめぐっていたときだ。
◎ 筆者は、『6秒間でストレスがとれる!』(ストレーベル 斉藤茂太訳 知的生き方文庫 三笠書房)に出会った。
→『6秒間でストレスがとれる!』が本棚にあるのを見つけた。その本に惹かれて、さっそく手に取って中身を見た。
◎本番で緊張しやすいのを自覚していた筆者は── その本を手に取ると、購入を決意、レジに向かった──。
→本番で緊張しやすいのを自覚していた筆者は、その本の購入を決意し、レジに向かった。
◎ この『6秒間でストレスがとれる!』は、当時、筆者の人生に、大きな影響を与えました。 そして、今も、その本質的な部分で、影響を与え続けています。
→ この『6秒間でストレスがとれる!』(ストレーベル 斉藤茂太訳 知的生き方文庫 三笠書房)は、当時の筆者の人生に大きな影響を与えました。
その大きな影響は、本質的な部分で今も続いています。
◎ 以上が、この本から、学んだことの柱です。
→ 以上が、この本から学んだことの柱です。
◎ そして、何より、“自分のコンディション(体調、心の調子、自由な思考…)を調えよう”という発想を与えてくれたという意味で── 「一生ものの知恵」 としての本質は、これまで、決して、色あせることも、くずれることもありませんでした。
→ 何より“自分のコンディション(体調、心の調子、自由な思考…)を整えよう”という発想は、「一生ものの知恵」として、これまで決して色あせることも、くずれることもありませんでした。
◎【今の筆者の解釈、今の筆者の実践&活用法、7C分析(7つのコンパスを活用した分析)…】
→【今の筆者の解釈、今の筆者の実践&活用法、7P分析(7つのパラダイムを活用した分析)…】
◎削除(受験生時代に購入した『6秒間でストレスがとれる!』は、兄への餞別としてプレゼントしたので── 中古で再購入しておいた『6秒間でストレスがとれる!』の方です)
◎ 先日、久々に全体的に読み返してみました。
気づいたのは── 筆者は、この本の内容を、いかに“そのままの形では実践してこなかったのか”ということでした。
→久々に全体的に読み返してみると、この本の内容を、筆者が“いかに、そのままの形で実践してこなかったのか”に気づきました。
◎◎筆者は、心の中で1、2、3と数えながら、呼吸をしていません!
→◎筆者は、心の中で1、2、3と数えながら呼吸をしていません。
◎◎筆者は、“心の中でほほえむ”という、そんな器用なことをできません!
→実際に、可能な限り、心地よくほほ笑みます。
(“心笑”です。 もしかしたら、英語の原著の“smile inwardly”の訳は、心ひそかにほほ笑む、人知れずほほ笑む…がよりふさわしいのかもしれません。 “心笑”の新しい意味付け方になりそうです)
→◎筆者は、やはり、“心の中でほほえむ”ことができません。
→実際に、可能な限り心地よくほほ笑みます。
※“心笑”です。もしかしたら、英語の原著の“smile inwardly”の訳は、心ひそかにほほ笑む、人知れずほほ笑む…がよりふさわしいのかもしれません。“心笑”の新しい意味付け方になりそうです。
◎◎「張りつめた心、平静な体」と、つぶやいたりしません!
→実際に、体をリラックスさせた状態で、頭を自由に働かせます。
→◎「張りつめた心、平静な体」と、つぶやいたりしません。
→実際に、体をリラックスさせた状態で、頭の中を(可能な限り)自由に働かせます。
◎ 英語のタイトルは、『QR The Quieting Reflex』──“落ち着いてくる反射”(or 静まってくる反射)──です。
何が落ち着いてくるのかと言うと、身体的、情動的なストレスが落ち着いてくると言うことだろうと思います。
→ 英語のタイトルは、『QR The Quieting Reflex』──“落ち着いている反射”(or 静まっている反射)──です。
何が落ち着いている(静まっている)のかと言えば、それは「身体的、情動的なストレス」です。
◎ 「張りつめた心、平静な体」の中の心は、頭脳〈mind〉──『アタマ』の方向のことであり、「心と体のリラックス」の中の心は、感情・情緒的な心〈heart〉──『カラダ』の方向のことだと理解すれば、矛盾が解消されると思います。
→ 「張りつめた心、平静な体」の中の心は、頭脳〈mind〉──『アタマ』の方向の心であり、「心と体のリラックス」の中の心は、感情・情緒的な心〈heart〉──『カラダ』の方向の心だと理解すれば、矛盾が解消されます。
◎この本『6秒間でストレスがとれる』は、
→この本『6秒間でストレスがとれる!』は、
◎ つまり、ブックサーフィンの始まりの1つとしても大切でした。
→つまり、ブックサーフィンの始まりの1つとしても重要でした。
◎ そして、また、この『6秒間でストレスがとれる』と、新たな本を重ね合わせることで、シナジェティックな効果が生まれ── より洗練された、自分にぴったりの知恵を育むこととなりました。
→ また、この『6秒間でストレスがとれる!』と新たな本を重ね合わせることで、シナジェティックな効果が生まれ、より洗練された、自分にぴったりの知恵を育むこととなりました。
◎ そして今──
“身体的、情動的には、ほどよくリラックスし(余計なストレスを緩和し)、頭脳は、自由に働き、想像力、ひらめきにあふれ、明晰さを保ちイキイキしている── そのようなコンディションを理想として目指し、維持しよう。
原始時代とは違い、現代の日常の多くの場面では、そのような状態でこそ、さまざまなベストパフォーマンスを達成できるし、健康的で、フルーツフルに生きられるよ”
そのような知恵を持ち、筆者は、それを活用しております。
→
そして今、次のような知恵を持ち、筆者は、それを活用しております。
「身体的&情動的には、ほどよくリラックスし(余計なストレスを緩和し)、頭脳的には、自由に働き、想像力、ひらめきにあふれ、明晰さを保ちイキイキしている──」 このようなコンディションを理想として目指し、可能な限り維持しよう。
原始時代とは違い、現代の日常の多くの場面では、そのような状態でこそ、さまざまなベストパフォーマンスを達成できるし、より健康的&フルーツフルに生きられるよ。
|
このような知恵を育むことを助けてくださった、さまざま本に、感謝いたしております。
『7つの習慣』
◎ なぜ、この本のタイトルに惹かれたのでしょうか?
→ なぜ、この本『7つの習慣』(スティーブン・R・コヴィー キングベアー社)のタイトルに惹かれたのでしょうか?
『3年 全国大学 国語入試問題詳解』
◎それは、受験生時代── →それは受験生時代──
◎該当部分 空白や改行の修正あり
◎ そして── 母が買ってきてくれた『3年 全国大学 国語入試問題詳解』を手にとった筆者は、驚いた。
→ 母が買ってきてくれた『3年 全国大学 国語入試問題詳解』を手にとった筆者は、驚いた。
◎ “果たして、その年の入試で合格できたのか、できなかったのか──” は、ここでは触れられません。 しかし、この本は、筆者に、かけがえのない出会い&ブックサーフィンのきっかけを提供してくれたという意味で、貴重でした。
→ “その年、果たして合格できたのかどうか” は、ここで触れられません。
しかし、この『3年 全国大学 国語入試問題詳解』(學燈社(“社”は示+土))との出会いは、かけがえのない新たな出会い&ブックサーフィンのきっかけを筆者に提供してくださったという意味で貴重でした。
◎ まず何より書くべきことは── 筆者が、小林秀雄氏の『中庸』に、初めて出会ったのは、まぎれもなく、この本の中であったことです。 (鹿児島大学 教育学部)
→ まず何より書くべきことは、筆者が小林秀雄氏の『中庸』に初めて出会ったのは、まぎれもなく、この本の中であったことです(p.373 鹿児島大学 教育学部)。
◎この『3年 全国大学 国語入試問題詳解』の中で、最もインパクトがあった文章が、この『中庸』であり── この『中庸』の中で、とりわけ、魅かれたのは、次の部分でした。
→当時、『3年 全国大学 国語入試問題詳解』の中で最もインパクトがあった文章が、この『中庸』であり── この『中庸』の中で、とりわけ惹かれたのは、次の部分でした。
◎ 「およそ正しく考えるという人間の能力自体の絶対的な価値の救助とか、回復とかがめざされているのだ。」
「いつも過不及があり、いつも変わっている現実に即して、自在に誤またず判断する精神の活動を言っているのだ。」
(下線は、筆者によります。 2つめの文章の全体は、“3Steps”とも、合致しているところがあると思います)
→
およそ正しく考えるという人間の能力自体の絶対的な価値の救助とか、回復とかがめざされているのだ。
(『中庸』 小林秀雄 (『3年 全国大学 国語入試問題詳解』 p.373 鹿児島大学 教育学部)) 下線は筆者によります。
いつも過不及があり、いつも変わっている現実に即して、自在に誤またず判断する精神の活動を言っているのだ。
(『中庸』 小林秀雄 (『3年 全国大学 国語入試問題詳解』 p.373 鹿児島大学 教育学部)) 下線は筆者によります。
|
| ※2つめの文章の全体は、“(人間レベルの)3ステップス”とも調和しています。 |
◎ 少なくとも受験生時代から、学生時代にかけての自分にとって、“中庸”がとても重要なものとなり── “人生の言葉”──座右の銘の一つとして活躍しました。
→ 少なくとも受験生時代から学生時代にかけての自分にとって、“中庸”が、とても重要なものとなり、“人生の言葉(座右の銘)”の一つとなりました。
◎なんとかしなければと思っていたから── だと思います。
→なんとかしなければと思っていたからだと思います。
◎(ストレスフルな状況で、バランスを崩して… って感じのものですね。『6秒間でストレスがとれる!』とも、シナジー的な関連があると思います)
→※ストレスフルな状況でバランスを崩して… って感じのものですね。『6秒間でストレスがとれる!』とも関連があると思います。
◎(もちろん、感覚、感性、感情… も、とても大切なものだと思います。
人が、正しく考えることを追求した究極のスタイルの果実が、“科学”なのだとすれば、
一方、人が感ずることを追求した究極のスタイルの果実が、“芸術”なのだと思います。
ここらあたりから、感ずることも、考えることも、両方大切──
という発想が育まれてきたのだと思います)
→
※もちろん、感覚、感性、感情… も、とても大切だと思います。
つまり、やはり、感ずることと考えることの両方が大切だと思います。
なお、かつて、正しく考えることを追求した究極のスタイルの果実が“科学”なのだとすれば、感ずることを追求した究極のスタイルの果実が“芸術”なのだと思っておりましたが、のちには、たとえ科学だけにおいても、感ずることと考えることの両方が大切だと気づきました。
◎ この「正しく考える」は、学生時代も、社会人になっても、ずっと大切な言葉であり続けました。
→ この「正しく考える」は、社会人になってから以降も、ずっと大切な言葉であり続けました。
◎ この「正しく考える」ことを重視していた姿勢があったからこそ──
のちに、書店で『論理的に考えるということ』山下正男著(岩波ジュニア新書99)を手に取り、購入を決意するに至ったのだと思います。
→ この「正しく考える」ことを重視していた姿勢があったからこそ、のちに、書店で『論理的に考えるということ』(山下正男 岩波ジュニア新書99)の購入に至ったのだと思います。
◎ その出会いは、まさに、“あの(経済的に切り詰めて)研究・執筆に専念していた時期”のものであり── “自分がやっていることって、科学? 科学ってそもそも何? 自分は、いったい何をやっているのだろう? 成果を、科学と調和したものにしたい。…” こういった考えが渦巻いていた頃でもありました。
→ その出会いは、まさに、“あの(経済的に切り詰めて)学問・執筆に専念していた時期”のものであり、「自分がやっていることは科学? 科学ってそもそも何? 自分は、いったい何をやっているのだろう? 成果を科学と調和したものにしたい。…」という考えが渦巻いていた頃でもありました。
◎ この『論理的に考えるということ』には、「中学初年級の学力さえあれば読み通すことができます。」と書かれています。 しかし、この本は、20代で読んだ筆者の眼からウロコを落としまくって下さりました。
→ この『論理的に考えるということ』には、「中学初年級の学力さえあれば読み通すことができます」と書かれています。
しかし、この本は、20代で読んだ筆者の眼からウロコを落としまくってくださりました。
◎ この本で、後々、筆者に最もインパクトを与えたのは、『II 大胆な推理』の部分でした。
(もちろん、『I 正しい証明』や『III 明確な表現』も、とても役立ちます。 感謝いたしております)
→ この本で、当時、筆者に最もインパクトを与えたのは、『II 大胆な推理』の部分でした。
※もちろん、今もインパクトを感じます。また、『I 正しい証明』や『III 明確な表現』も、とても役立ちます。感謝いたしております。
◎例えば、次のようなキーセンテンス、キーワードが、おおいに心を動かされました。
「帰納法には冒険的な要素があり」
「つぎに帰納法についてですが、これは個々の経験的な事例を集め、そこから、一般的な結論を一気にひきだすという手続きです。この「一気に」という点が帰納法の大切な特徴です。」
「帰納法的飛躍」
「一般的な文章は、たった一つの例外でひっくりかえされてしまいます。だから、よほど慎重に考えたうえでないと、一般的な文章をつくりあげてはならないのです。」
「一つの全体的な構造というものをみつけなければほんとうの発見とはいえないのです。… そうした挑戦してみるに価いするものです」
「類推法」
「人間や人間社会に関するのはやさしそうでたいへんむつかしいのです。自然に関する体系の方がやさしいといえます」
…
→
例えば、次のようなキーセンテンス&キーワードに、おおいに心を動かされました。
『帰納法には冒険的な要素があり』
『つぎに帰納法についてですが、これは個々の経験的な事例を集め、そこから、一般的な結論を一気にひきだすという手続きです。この「一気に」という点が帰納法の大切な特徴です。』
『帰納法的飛躍』
『一般的な文章は、たった一つの例外でひっくりかえされてしまいます。だから、よほど慎重に考えたうえでないと、一般的な文章をつくりあげてはならないのです。』
『一つの全体的な構造というものをみつけなければほんとうの発見とはいえないのです。… そうした挑戦してみるに価いするものです』
『類推法』
『人間や人間社会に関するのはやさしそうでたいへんむつかしいのです。自然に関する体系の方がやさしいといえます』
…
(『論理的に考える』 山下正男 岩波ジュニア文庫99) 一部省略。『』は筆者によります。
|
◎今、読み返してみてもインパクトを感じます。
→やはり、今、読み返してみてもインパクトを感じます。
◎ この本は、“科学とは何か?”についてのヒントという果実として、筆者に影響を与えて下さりました。
→ この本は、「“科学とは何か?”についてのヒント」という果実として、筆者に影響を与えてくださりました。
◎ 上でも述べたように、やはり、“人が、正しく考える”ことを追求する営みの果実が、“科学”なのだと思います。
“果たして、自分は、今、正しく考えられているだろうか?”
“科学とは、いったい何?”“自分がやっていることって、本当に科学?”
という発想は、科学をするにあたって必要不可欠な要素なのだろうと思います。
こういった発想の大切さを感じる中で、展開されてきたブックサーフィンの具体例が──
→「果たして、自分は正しく考えられているだろうか?」「科学とは、いったい何?」「自分がやっていることは、本当に科学?」といった発想の大切さを感じ続ける中で、のちに展開されたブックサーフィンの具体例が──
◎文字サイズ変更あり
『99・9%は仮説 思い込みで判断しないための考え方』 竹内薫 光文社新書
『科学の終焉』 ジョン ホーガン[著] 筒井康隆[監修] 竹内薫[翻訳]
『わたしたちはなぜ科学にだまされるのか』 ロバート・L.パーク[著] 栗木さつき[翻訳]
『ストリング理論は科学か』 ピーター ウォイト[著] 松浦俊輔[翻訳]
『新しい科学論 事実は理論をたおせるか』 村上陽一郎 講談社ブルーバックス
『あなたにとって科学とは何か』 柴谷篤弘 みすず書房
『科学革命の構造』 トーマス・クーン[著] 中山茂[翻訳] みすず書房
『新版 科学論の展開──科学と呼ばれているものは何なのか?──』
A.F.チャルマーズ[著] 高田紀代志[翻訳] 佐野正博[翻訳]
『科学の大発見はなぜ生まれたか 8歳の子供との対話で綴る科学の営み』
ヨセフ・アガシ[著] 立花希一[翻訳] 講談社ブルーバックス
『科学哲学』 小林道夫 産業図書
『科学哲学の冒険』 戸田山和久 NHKブックス
『偉大なる失敗』 マリオ・リヴィオ[著] 千葉敏生[翻訳]
…
→
『99・9%は仮説 思い込みで判断しないための考え方』 竹内薫 光文社新書
『科学の終焉』 ジョン ホーガン[著] 筒井康隆[監修] 竹内薫[翻訳]
『わたしたちはなぜ科学にだまされるのか』 ロバート・L.パーク[著] 栗木さつき[翻訳]
『ストリング理論は科学か』 ピーター ウォイト[著] 松浦俊輔[翻訳]
『新しい科学論 事実は理論をたおせるか』 村上陽一郎 講談社ブルーバックス
『あなたにとって科学とは何か』 柴谷篤弘 みすず書房
『科学革命の構造』 トーマス・クーン[著] 中山茂[翻訳] みすず書房
『新版 科学論の展開──科学と呼ばれているものは何なのか?──』
A.F.チャルマーズ[著] 高田紀代志[翻訳] 佐野正博[翻訳]
『科学の大発見はなぜ生まれたか 8歳の子供との対話で綴る科学の営み』
ヨセフ・アガシ[著] 立花希一[翻訳] 講談社ブルーバックス
『科学哲学』 小林道夫 産業図書
『科学哲学の冒険』 戸田山和久 NHKブックス
『偉大なる失敗』 マリオ・リヴィオ[著] 千葉敏生[翻訳]
…
◎シナジー的な効果を与えて下さっているように思います。
→シナジー的な効果を与えてくださっているように思います。
◎・小林秀雄『常識について』
・三木清『人生論ノート』(「健康について」…)
・中村雄二郎『哲学の現在』
→『常識について』 小林秀雄 角川文庫
『人生論ノート』 三木清 新潮文庫
『哲学の現在』 中村雄二郎 岩波文庫
◎そして、それらの中では、当時、とりわけ、『常識について』が、筆者の中でヒットしました。
『常識について』の中では、パートIVの、「読書について」「文化について」「喋ることことと書くこと」「常識について」… など、比較的、抽象的なテーマを扱う文章──“普遍性、一般性”を追求したような文に魅かれました。 (そのあたりは、やはり、理系的な性格からの影響があるのかもしれません)
→ それらの中では、当時、とりわけ『常識について』が筆者の中でヒットしました。
『常識について』の中では、パートIVの「読書について」「文化について」「喋ることことと書くこと」「常識について」… など、比較的、抽象的なテーマを扱う文章──“普遍性や一般性”を追究した文章に惹かれました。
※そのあたりは、やはり、理系的な性格の影響があると思います。
◎そして── その後、小林秀雄にはまりました。
→ その後、小林秀雄に、はまりました。
◎ 次々と購入し、つまみ読みしました。(読みたいなと思った部分だけ、読ませていただきました)
小林秀雄ファンになりました。
(『新潮日本文学アルバム 小林秀雄』を購入したほどです)
→ 次々と購入し、つまみ読みしました(読みたいなと思った部分だけ、読ませていただきました)。
小林秀雄ファンになりました(『新潮日本文学アルバム 小林秀雄』を購入したほどです)。
◎(「読書について」の中の「君は君自身でい給え」の言葉に、当時、とても共感していましたし、今も共感いたしております)
→※「読書について」の中の「君は君自身でい給え」の言葉に、当時、とても共感しておりましたし、今も共感しております。
◎ しかし、その影響は、とても大きいものがありました。
→ しかし、その影響は、とても大きかったでした。
◎ 近年、『3年 全国大学 国語入試問題詳解』を、久々に眺めてみました。
→ のちに、『3年 全国大学 国語入試問題詳解』を、久々に眺めてみました。
◎・滝浦静雄『「自分」と「他人」をどうみるか─新しい哲学入門』
〈エピローグ 日本的「こころ」の概念〉の一節(一部省略)
・大庭みな子『女の男性論』〈I《自己を対象化する「他人の眼」》〉
・秋山駿『人生の検証』〈身〉の一部
・鈴木孝夫『閉ざされた言語・日本語の世界』
〈第四章 日本文化と日本人の言語観《相手依存の自己限定》〉の一節
・養老猛司『歴史と普遍』の一節
・梅田卓夫・清水良典・服部左右一・松川吉博編『高校生のための批評入門』
〈7思考するまなざし《[手帖7]モノをみつめる》〉
・池内了『次元と言葉』
・三枝博音『日本の思想文化』
・大岡玲『「物語ること」の使命』
・戸井田道三『色つやの日本文化』
・『成長の限界ーローマ・クラブ「人類の危機」レポート
(当時、思いっきり素通りしてしまったな── と思ってしまいます)
・小林秀雄『無私の精神』
・大野晋『日本語と世界』
・山本信の文──「心身問題」についての文
(「心身問題」というキーワードに、この本の中で出会っていたのか、ということを、この再読を通じて、はっきり認識しました。)
・・・
→
・滝浦静雄『「自分」と「他人」をどうみるか─新しい哲学入門』
〈エピローグ 日本的「こころ」の概念〉の一節(一部省略)(p.36 早稲田大学 政治経済学部)
・大庭みな子『女の男性論』〈I《自己を対象化する「他人の眼」》〉 (p.118 中央大学 法学部法律学部)
・秋山駿『人生の検証』〈身〉の一部 (p.125 明治大学 商学部)
・鈴木孝夫『閉ざされた言語・日本語の世界』
〈第四章 日本文化と日本人の言語観《相手依存の自己限定》〉の一節(p.138 桜美林大学 文学部)
・養老猛司『歴史と普遍』の一節 (p145 成蹊大学 経済学部)
・梅田卓夫・清水良典・服部左右一・松川吉博編『高校生のための批評入門』
〈7思考するまなざし《[手帖7]モノをみつめる》〉(p.152 東洋大学 経営学部)
・池内了『次元と言葉』(p.286 東京大学 前期-文科)
・三枝博音『日本の思想文化』(p.296 京都大学 後期)
・大岡玲『「物語ること」の使命』(p.334 東北大学)
・戸井田道三『色つやの日本文化』(p.338 千葉大学 文学部・法経学部)
・山本信の文──「心身問題」についての文(p.387 慶応義塾大学 文学部)
・『成長の限界ーローマ・クラブ「人類の危機」レポート(p.392 慶応義塾大学 商学部B)
・小林秀雄『無私の精神』(p.394 早稲田大学 第一文学部)
・大野晋『日本語と世界』(p.398 独協大学 外国語学部)
…
◎ かつて、素通りしたり、すり抜けていった多くの言葉・文章たちが、
今、興味深く感じられ、心に、ひっかかるようなってきているということ──。
→ かつて、素通りしたり、すり抜けていったりした多くの言葉・文章たちが、
のちに、興味深く感じられ、心に、ひっかかるようなっているということ──。
◎ 少しは、成長してきているのでしょうか?
→ 少しは、成長したのでしょうか?
◎ もしかしたら、“遠回りブックサーフィン&時間差ブックサーフィン”と言うのもありなのかもしれません。
→ もしかしたら、“遠回りブックサーフィン&時間差ブックサーフィン”も、ありなのかもしれません。
◎ まだまだ、出会うべき本、読むべき本があるのではないか── と感じます。
→ まだまだ、出会うべき本、読むべき本があるのではないかとも思います。
◎ そして、時間や機会があれば、新たなブックサーフィンをここからも始めてみたい── と“お楽しみ袋”が膨らむのでした。
→ そして、「時間や機会があれば、新たなブックサーフィンをここからも始めてみたい」 と思うのでした。
◎
特殊な事例をあつかったものより、普遍性を追究した文章──。
→ 特殊な事例をあつかったものより、普遍性や一般性を追究した文章──。
◎ こういう文章や言葉に、今の自分は、より魅かれるようです。
→ こういう文章に、今の自分は、より惹かれるようです。
◎ そして、つまり、やはり“本は相性である”ということを実感するのでした。
→ そして、つまりは、“本が相性である”ことを実感するのでした。
◎(こういった筆者が、「『7つのコンパス』【物語3.05】」のような作品を育てているのだから、人生、不思議でおもしろいですね。
子供の頃、好きな物語を楽しみながら読んだ経験(ズッコケ三人組シリーズ、青葉学園物語シリーズ、ジャイアントゴーグ、我が輩は猫である…)、若者期に物語(北の国から89帰郷、人生の贈り物、北の国から前編・後編シナリオ)にはまった経験、社会人になって、ハリー・ポッター(1-3)( 賢者の石、秘密の部屋、アズカバンの囚人)に感動した経験… があればこそだと思います。
そういう目で見れば、たしかに、単なるフィクション&物語ではなく、論理的&抽象的な文章、普遍性をも追究した文章をも含む物語なので、“感じながら”(楽しみながら、悲しみながら…)だけでなく、“考えながら”育てているとも言え── バランスがとれていると言えるのかもしれません)
→※こういった筆者が、「『7つのパラダイム』【物語3.08】」のような作品を育てているのですから、人生、不思議でおもしろいですね。
子供の頃、好きな物語を楽しみながら読んだ経験(ズッコケ三人組シリーズ、青葉学園物語シリーズ、ジャイアントゴーグ、我が輩は猫である…)、若者期に物語(北の国から89帰郷、人生の贈り物、北の国から前編・後編シナリオ)にはまった経験、社会人になって、ハリー・ポッター(1-3)( 賢者の石、秘密の部屋、アズカバンの囚人)に感動した経験… があればこそだと思います。
そういう目で見れば、たしかに、単なるフィクション&物語ではなく、論理的&抽象的な文章、普遍性&一般性を追究した文章も含む物語ですので、“感じながら”(楽しみながら、悲しみながら…)だけでなく、“考えながら”育てているとも言え── バランスがとれているのかもしれません。
◎シナジェティック・リーディングの候補とも言えると思います。
→感謝いたしております。
◎テーブルの幅の修正あり
◎
| 『常識について』 小林秀雄 |
『中庸』(“正しく考える”“いつも過不及ががあり、いつも変わっている現実に即して、自在に誤またず判断する精神の活動を言っているのだ。”) 『読書について』(“君は君自身でい給え”)… ハッとするような言葉、心の糧になるような言葉があります。 |
『論理的に考えるということ』
山下正男 岩波ジュニア新書99 |
「帰納法には冒険的な要素があり」
「つぎに帰納法についてですが、これは個々の経験的な事例を集め、そこから、一般的な結論を一気にひきだすという手続きです。この「一気に」という点が帰納法の大切な特徴です。」
「帰納法的飛躍」
「一つの全体的な構造というものをみつけなければほんとうの発見とはいえないのです。… そうした挑戦してみるに価いするものです」…
研究する筆者を勇気づける言葉たちにあふれています。 |
『99%仮説である』 竹内薫 光文社新書
|
筆者の論文には、仮説が多く立てられています。
『99%仮説である』というくらいだから── という勇気を頂いております。
|
科学とは、何かについての本──
『科学の終焉』
ジョン ホーガン[著] 筒井康隆[監修] 竹内薫[翻訳]
『わたしたちはなぜ科学にだまされるのか』
ロバート・L.パーク[著] 栗木さつき[翻訳]
『ストリング理論は科学か』
ピーター ウォイト[著] 松浦俊輔[翻訳]
『あなたにとって科学とは何か』
柴谷篤弘 みすず書房
『科学革命の構造』
トーマス・クーン[著] 中山茂[翻訳] みすず書房
『新版 科学論の展開
──科学と呼ばれているものは何なのか?──』
A.F.チャルマーズ[著] 高田紀代志[翻訳] 佐野正博[翻訳]
『科学の大発見はなぜ生まれたか
8歳の子供との対話で綴る科学の営み』
ヨセフ・アガシ[著] 立花希一[翻訳] 講談社ブルーバックス
『偉大なる失敗』
マリオ・リヴィオ[著] 千葉敏生[翻訳]
…
|
研究を進めるにあたって、さまざまなことを考えさせて頂きました。
励みになったり背中を押してくださった本もあります。
|
『新しい科学論 事実は理論をたおせるか』
村上陽一郎 講談社ブルーバックス |
さまざまな観測結果の解釈は、理論と深く結びついていることを
学びました。
“連星パルサーの観測結果”や“マイケルソン・モーレーの実験”…
の新たな解釈を育てる筆者の背中を押してくださっています。
|
『創造の世界 湯川秀樹自選集〈4〉』
湯川秀樹 朝日新聞社 |
湯川秀樹先生が、“科学とは、何か”についても、
考えておられることを知りました。
特に“直観の大切さ”を説く文章に励まされました。
アップする勇気をあたえてくださりました。 |
| 『科学哲学』 小林道夫 産業図書 |
2015年春、アップしたあとの引っ越し作業の途中で、出会いました。
かつて、古本屋さんで購入し、長らく“積ん読”状態で、
存在を忘れてしまっていたこの本──
この本のおかけで、“科学的実在論”のキーワードに出会いました。
筆者の研究の立場は、“科学的実在論”を支持する方向の
ものであるようです。 |
『科学哲学の冒険』 戸田山和久 NKKブックス
|
“科学的実在論”のキーワードからのブックサーフィン
の結果として、2015年春、出会いました。
仮説を立てること(アブダクション)や類推法が、
帰納法の一種であることをはっきりと認識できました。
|
| →『人生論ノート』 |
|
| →『哲学の現在』 |
|
| →“心身問題”という言葉 |
3Steps理論には、“心身問題”を解消できる
ポテンシャルがあると言えるのかもしれません。 |
→
『常識について』
小林秀雄 角川文庫 |
『中庸』(『正しく考える』『いつも過不及ががあり、いつも変わっている現実に即して、自在に誤またず判断する精神の活動を言っているのだ』) 『読書について』(『君は君自身でい給え』)…
ハッとするような言葉、心の糧になるような言葉があります。 |
『論理的に考えるということ』
山下正男 岩波ジュニア新書99 |
『帰納法には冒険的な要素があり』
『つぎに帰納法についてですが、これは個々の経験的な事例を集め、そこから、一般的な結論を一気にひきだすという手続きです。この「一気に」という点が帰納法の大切な特徴です』
『帰納法的飛躍』
『一つの全体的な構造というものをみつけなければほんとうの発見とはいえないのです。… そうした挑戦してみるに価いするものです』…
学問する筆者を励ましてくださりました。 |
『99%仮説である』
竹内薫 光文社新書
|
励まされました。 |
科学とは、何かについての本──
『科学の終焉』 ジョン ホーガン[著]
筒井康隆[監修] 竹内薫[翻訳]
『わたしたちはなぜ科学にだまされるのか』
ロバート・L.パーク[著] 栗木さつき[翻訳]
『ストリング理論は科学か』
ピーター ウォイト[著] 松浦俊輔[翻訳]
『あなたにとって科学とは何か』
柴谷篤弘 みすず書房
『科学革命の構造』 トーマス・クーン[著]
中山茂[翻訳] みすず書房
『新版 科学論の展開
──科学と呼ばれているものは何なのか?──』
A.F.チャルマーズ[著] 高田紀代志[翻訳]
佐野正博[翻訳]
『科学の大発見はなぜ生まれたか
8歳の子供との対話で綴る科学の営み』
ヨセフ・アガシ[著] 立花希一[翻訳]
講談社ブルーバックス
『偉大なる失敗』
マリオ・リヴィオ[著] 千葉敏生[翻訳]
…
|
学問を進めるにあたって、さまざまなことを考えさせて頂きました。励みになりました。
|
『新しい科学論 事実は理論をたおせるか』
村上陽一郎 講談社ブルーバックス |
さまざまな観測結果の解釈が理論と深く結びついていることを学びました。
“連星パルサーの観測結果”や“マイケルソン・モーレーの実験”… の新たな解釈を育てる筆者の背中を押してくださりました。
|
『創造の世界 湯川秀樹自選集〈4〉』
湯川秀樹 朝日新聞社 |
おかげで、湯川秀樹が“科学とは何か”についても考えておられていたことを知ることができました。特に“直観の大切さ”を説く文章に励まされました。アップする勇気をあたえてくださりました。 |
『科学哲学』
小林道夫 産業図書 |
2015年春、この本のおかけで、“科学的実在論”のキーワードに出合いました。筆者は“科学的実在論”を支持しています。
|
『科学哲学の冒険』
戸田山和久 NKKブックス
|
“科学的実在論”のキーワードをきっかけにしたブックサーフィンにより、2015年春に出会いました。おかげで、仮説を立てること(アブダクション)や類推法が、帰納法の一種であることをはっきりと認識できました。
|
『人生論ノート』
三木清 新潮文庫 |
受験生当時、『健康について』(p.308 大阪大学 前期)に惹かれました。
『何が自分の為になり、何が自分の害になるか、の自分自身の観察が、健康を保つ最上の物理学であるということには、物理学の規則を超えた智慧がある。──私はここにベーコンの言葉を記すのを禁ずることができない。これは極めて重要な要請訓である。しかもその根底にあるのは、健康は各自のものであるという、単純な、単純な故に敬虔なとさえいい得る真理である』『現代人はもはや健康の完全なイメージを持たない。そこに現代人の不幸の大きな原因がある。如何にして健康の完全なイメージを取り戻すか、これが今日の最大の問題の一つである』…
これがきっかけで『人生論ノート』の購入に至りました。“従来の哲学”のイメージを育んでくださっていた本の一つだと思います。 |
『哲学の現在』
中村雄二郎 岩波文庫
|
受験生当時、『II感覚と想像の働き』(p.302 お茶の水女子大学)に惹かれました。
『毎日通いなれている駅までの道を、ある日曜日に散歩のためにのんびり歩いてみる。すると、通勤のために歩いているときには気がつかなかった道筋のほんの片隅に山茶花の木が紅白色の美しい花をつけているのが目に入ってびっくりしたり、道筋の或るところからひらけて見える青空のさわやかさに息を呑んだのりする』『このように私たち人間にあって、思い、考えるということは、その根本において感じることも含んでいるのである』…
これがきっかけで『哲学の現在』の購入に至りました。“従来の哲学”のイメージを育んでくださっていた本の一つだと思います。 |
『山本信の文』(p.387 慶応義塾大学 文学部)
※厳密には、『マイ・ブックサーフィン』では
ありませんが、ここに挙げさせていただきます。 |
“心身問題”というキーワードが示されています。
3ステップス哲学には、“心身問題”を解消できるポテンシャルがあると思います。
心(認識、意識、表象、想像、感情、情緒、意志…)は、細胞社会レベル&人間レベルで生成している“内面”です(潜在意識、疲れ、ストレス、本能…は、主に細胞社会レベルで生成しています)。
身体は、細胞社会(脳…)レベル、細胞レベル、生体機能分子社会レベル、生体機能分子レベル…で生成している“外面”です。
両者は同時に共存しています。
※なお、表象(∈心)の一部は、自然(nature)と調和していたり、自然(nature)から乖離していたりします。
なお、たとえ自然(nature)から乖離していても(例えば、サンタクロース、ファンタジー…)、For Life(=For“『In』&『Out』”)路線である限りは、多様な人間(人生)のあり方が尊重され続けてよいのだと思います。 |
『目からウロコの文化人類学入門』
◎中古本屋さんで、この本のタイトル『目からウロコの文化人類学』の中の“人類”に魅かれて、手に取ってみた。
→中古本屋さんで、タイトル中の“人類”に惹かれて『目からウロコの文化人類学』を手に取ってみた。
◎ この記述から、筆者は、「『Against』→『For』の過程で作り出されたもののすべてが、文化であるのだ」と言えると思いました。
→ この記述から「『Against』→『For』の過程で作り出されたすべてが、文化である」と思いました。
◎そして、この記述に、さらに、筆者の中にあった『文化(culture)には栽培するという語感がともなうこと』(小林秀雄氏の「文化について」の中の記述)と、「フルーツには本来『For』(“For Life”)の意味があること」が結びつきました。
→さらに、この記述に、筆者の中にあった『文化(culture)には栽培するという語感がともなうこと』(小林秀雄の『文化について』の中の記述)と「フルーツには本来『For』(“For Life”)の意味があること」が結びつきました。
◎
『文化人類学者は人というものをの研究をめざすから、研究対象は当然、後者、広い方の文化である。つまり高級であろうがなかろうが、人が作り出したものすべて、ということになるが、もう少し厳密な定義となると、文化人類学者の数だけあるといってもよい。そこで本書では、文化を「人が生きることを阻害するものに対する対抗手段として作り出したすべてのもの」と定義することにする。』
『目からウロコの文化人類学入門』 p.12 斗鬼正一著 ミネルヴァ書房
下線は、筆者による |
→
文化人類学者は人というものをの研究をめざすから、研究対象は当然、後者、広い方の文化である。つまり高級であろうがなかろうが、人が作り出したものすべて、ということになるが、もう少し厳密な定義となると、文化人類学者の数だけあるといってもよい。そこで本書では、文化を「人が生きることを阻害するものに対する対抗手段として作り出したすべてのもの」と定義することにする。
(『目からウロコの文化人類学入門』 p.12 斗鬼正一 ミネルヴァ書房) 下線は、筆者によります。 |
◎ ※なお、小林秀雄氏の「文化について」の中の記述とは次の部分です。
『だけどもカルチュアという言葉は西洋人にとっては、母国語としてのはっきりとした語感を持っているはずだ。耳に聞いただけで誤解しようがないのです。カルチュアというのは畑を耕して物を作る栽培という意味だ。カルチュアという言葉にしたってけっして単一な意味ではないが、どんな複雑な意味に使われようと、カルチュアと聞けば、西洋人には栽培という意味が含まれていると感ずる。これが語感である』
(『常識について』or『栗の木』 小林秀雄 下線は、筆者による)
|
※フルーツは、本来、『For』(“For Life”)の意味を持っている一方、逆に、『白雪姫』に登場する毒リンゴを含む、毒フルーツは、『Against』(“Against Life”)の意味を持っています。
→
※なお、小林秀雄の『文化について』の中の記述とは次の部分です。
だけどもカルチュアという言葉は西洋人にとっては、母国語としてのはっきりとした語感を持っているはずだ。耳に聞いただけで誤解しようがないのです。カルチュアというのは畑を耕して物を作る栽培という意味だ。カルチュアという言葉にしたってけっして単一な意味ではないが、どんな複雑な意味に使われようと、カルチュアと聞けば、西洋人には栽培という意味が含まれていると感ずる。これが語感である。
(『文化について』小林秀雄 p184『常識について』角川文庫 p.51-52『栗の木』 講談社) 下線は、筆者によります。
|
◎ その結果──
筆者は、「文化とは、“フルーツ”である」と思いました。
→ その結果、「文化はフルーツである」という考えに至りました。
◎ 「生きるために、育まれたフルーツ」
こういった“(栽培された、おいしい)フルーツ”に、文化は相当していると理解できると思いました。
→ 「生きるために育まれたフルーツ」
…
こういった“(栽培された、おいしい)フルーツ”に、文化は相当していると思いました。
◎ 以上より、筆者は、文化とは、
『Against』→『For』の過程で栽培されたフルーツ(厳密には“フルーツFor Life”)である──
という定義を採用することことにしました。
文化とは、
『Against』→『For』の過程で栽培されたフルーツ(厳密には“フルーツFor Life”)である。 |
→
以上より、文化について、筆者は次の定義を採用することにしました。
文化とは、
『Against』→『For』の過程で栽培されたフルーツ(厳密には“フルーツFor Life”)である。 |
◎ このような文化の定義付けを確立させて以来── 筆者は、文化という言葉に出会う度に(少なくとも)“フルーツである”と解釈するようになりました。
→ このような文化の定義付けを確立させて以来、筆者は、文化という言葉に出合う度に(少なくとも一度は)“フルーツである”と解釈してみるようになりました。
◎ 文化── 科学も、技術も、哲学も、芸術も、言語も、生活習慣も、ライフスタイルも、生活様式も、風習も、マナーやエチケットも、倫理観も、知恵や工夫も、健康的な生活も、レシビも、小説もシナリオも、ドラマも映画も… どれもこれも、人類が栽培してきた、『Against』を乗り越えるために育んできた、かけがえのないフルーツ(厳密には“フルーツFor Life”)なのだと思う時──
どれもこれも、いとおしいもののように感じられてきます。
→
「哲学、倫理、科学、技術、芸術、言語、生活習慣、ライフスタイル、生活様式、風習、マナーやエチケット、知恵や工夫、健康的な生活、レシビ、小説、シナリオ、ドラマ、映画…」を含むあらゆる文化が、人類が『Against』を乗り越えるために育んだ(栽培した)かけがえのないフルーツ(厳密には“フルーツFor Life”)なのだと思うとき── どれもこれも、いとおしいと感じられます。
◎ 違うからこそ、シナジーが生まれえます。
同じだったら、シンクロ(共鳴、共感…)しえます。
→ 同じであれば、シンクロ(共鳴、共感…)し合えます。
たとえ違くても、シナジーが生じえます。
◎ お互いにフルーツを持ち寄り、お互いのフルーツを味わい合い、理解し合う中で、調和、融和、平和、協調、シナジー… にたどり着けたなら、ありがたく、うれしいことだと思います。
→ お互いにフルーツを持ち寄り、お互いのフルーツを味わい合いながら(理解し合いながら)、調和、融和、平和、協調… にたどり着けたなら、ありがたく、うれしいことだと思います。
◎ 例えば、「文化は、フルーツの一部である」ということに気づきました。
→ 例えば、「文化はフルーツの一部であること」に気づきました。
◎ したがって、「文化は、フルーツである」は正しくても、「フルーツは、文化である」は、必ずしも正しくないことになります。
→ したがって、「文化はフルーツである」が正しくても、「フルーツは文化である」は必ずしも正しくないことになります。
◎ フルーツ(厳密には“フルーツFor Life”)が、文化であるために、必要な条件は何なのか?
→ フルーツが文化であるために必要な条件は何でしょうか?
◎ 例えば、日本人にとって庶民的なフルーツ、みかん、りんご、イチゴ… といった多くの方々が味わっているフルーツは、日本人にとっての文化と言える一方── 多くの日本人にとって比較的珍しいフルーツ、「マンゴスチン、ドラゴンフルーツ、バッションフルーツ…」は、多くの日本人にとって、“文化”には至っていないと言えるのだと思います。
→※例えば、日本人にとって庶民的なフルーツ、「みかん、りんご、いちご…」を含む多くの方々が味わっているフルーツは、日本人にとっての文化だと言える一方── 多くの日本人にとって比較的珍しいフルーツ、「マンゴスチン、ドラゴンフルーツ、バッションフルーツ…」を含む多くの方々が味わっていないフルーツは、日本人にとっての文化だと言えないのだと思います。
◎ また、例えば、文明とは、本来は、「より普遍的なフルーツ(厳密には“フルーツFor Life”)」((地域(国、民族、言語… )をこえて、時代をこえて)より多くの人々の間で広まっているフルーツ(厳密には“フルーツFor Life”))であることに気づきました。
→ さらに、例えば、文明とは、本来「より普遍的なフルーツ((地域(国、民族、言語… )をこえて、時代をこえて)より多くの人々の間で広まっているフルーツ)」であることに気づきました。
◎ つまり、本来、文明は、文化(厳密には“フルーツFor Life”の一部)の一部に相当することに気づきました。
→ さらに、例えば、文明とは、本来「より普遍的なフルーツ(厳密には“フルーツFor Life”)」((地域(国、民族、言語… )をこえて、時代をこえて)より多くの人々の間で広まっているフルーツ(厳密には“フルーツFor Life”))であることに気づきました。
つまり、本来、文明は、文化の一部に相当することに気づきました。
◎ ※したがって、本来は、“文明”には、「人類に恩恵を与えてくれる文明」、すなわち、「文明“For Life”」が意味あることになります。
すなわち、文明とは(厳密には)文明“For Life”のことであると言えるのだと思います。
(それは、フルーツとは(厳密には)フルーツ“For Life”のことであり、文化とは(厳密には)文化“For Life”のことであるのと同様です)
よって、逆に、「人類に脅威を与えてしまう文明」、すなわち、「文明“Against Life”」という意味を持つ文明は、(本来の)文明ではなく、“毒文明”であるということになると思います。
一方、文化も、気をつけないと、ときに脅威になりうるということにも、ブックサーフィンを通じて気づきました。
すなわち、文化とは、厳密には文化“For Life”のことであり、毒文化とは、文化“Against Life”のことであると言えることに気づきました。(それは、フルーツとは(厳密には)フルーツ“For Life”のことであり、毒フルーツとはフルーツ“Against Life”のことであると言えることと同様です)
そして、例えば、フルーツの一部が文化であり、文化の一部が文明であるように── 毒フルーツの一部が毒文化であり、毒文化の一部が毒文明であると言えることにも気づきました。
…
→
したがって、本来、“文明”とは「人類に恩恵を与えてくれる文明」、「文明“For Life”」であることになります(それは、フルーツとは(本来)フルーツ“For Life”のことであり、文化とは(本来)文化“For Life”のことであるのと同様です)。
※逆に「人類に脅威を与えてしまう文明」、「文明“Against Life”」ならば、(本来の)文明ではないことになります(それは、文化“Against Life”ならば、(本来の)文化ではないこと、フルーツ“Against Life”ならば、(本来の)フルーツではないことと同様です)。
…
◎こういった気づきを含めて、『目からウロコの文化人類学』をきっかけとしたブックサーフィン、すなわち、以下のような“文化”や“文明”に関する本との出会いは、「さまざまな気づき、ヒント、目からウロコ体験…」を与えて下さり、文化観や文明観を深めて下さりました。
→『目からウロコの文化人類学』をはじめとする、以下のような“文化”や“文明”に関する本との出会いは、「さまざまな気づき、ヒント、目からウロコ体験…」を与えてくださりました。
おかげで、『文化とはフルーツである』を含め、筆者は文化観や文明観を深めることができました。
◎追加
『目からウロコの文化人類学』
斗鬼正一 ミネルヴァ書房 |
「文化とはフルーツである」という考えに至るための貴重なヒントを提供してくださりました。 |
◎テーブルの右サイドの文字を小さくする。
◎
『文化について』 小林秀雄
(『常識について』or『栗の木』) |
| 『文明と人間 科学・技術は人間を幸福にするか』 志村忠生 丸善ブックス |
| 『文化人類学がよ〜くわかる本 ポケット図解』 杉下龍一郎 秀和システム |
| 『文化人類学入門』 山下普司編 弘文堂 |
『自然と文化の人類学』
葭田光三 八千代出版 |
『異文化の共存』
岩波講座文化人類学第8巻 岩波書店 |
| 『共生の文化人類学 暮らしのトポスと経験知』 渡辺重行 学陽書房 |
『異文化とつき合うための心理学』
金沢吉示 誠信書房 |
『文化としての科学/技術』
(村上陽一郎 岩波書店)
|
『文明の中の科学』
(村上陽一郎 青土社) |
→
『文化について』 小林秀雄
『常識について』角川文庫 『栗の木』 講談社 |
| 『文明と人間 科学・技術は人間を幸福にするか』 志村忠生 丸善ブックス |
| 『文化人類学がよ〜くわかる本 ポケット図解』 杉下龍一郎 秀和システム |
『文化人類学入門』
山下普司編 弘文堂 |
『自然と文化の人類学』
葭田光三 八千代出版 |
『異文化の共存』
岩波講座文化人類学第8巻 岩波書店 |
| 『共生の文化人類学 暮らしのトポスと経験知』 渡辺重行 学陽書房 |
『異文化とつき合うための心理学』
金沢吉示 誠信書房 |
『文化としての科学/技術』
村上陽一郎 岩波書店
|
『文明の中の科学』
村上陽一郎 青土社 |
◎最後のテーブルの下にあった次の部分を削除
中には、必ずしも『目からウロコの文化人類学』だけがきっかけではなかった本もあります。
しかし、いずれにしても、『目からウロコの文化人類学』が与えて下さった文化観(『文化とはフルーツである』)のおかげで、より理解が深まっていたのは確かです。
もちろん、『目からウロコの文化人類学』にも、心から感謝いたしております。
2019年11月24日 ひるねスイーツ1.40
◎
 → →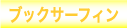
ブックサーフィン
マイ・ブックサーフィン
◎新しいページの追加
『人間性の心理学』
『7つの習慣』
◎
それは、筆者が、学生時代の時だった。
→
それは学生時代のことだった。
◎該当部分 空白&改行の修正あり
◎該当部分 魅かれた→惹かれた
◎購入を決意── →購入を決意。
◎ なぜ、この本に惹かれたのでしょうか?
1つは、
→ なぜ、この本のタイトルに惹かれたのでしょうか?
それは、
◎を持ってしまったことを── 今でも覚えています。→が生じてしまったことを、今でも覚えています(笑)。
◎感じさせてくれた── という効果もあったのだろうと思います。
→感じさせてくれたという効果もあったのだと思います。
◎ もう1つは、中身を見て初めて分かった、『7つの習慣』がもつ、“本質を見失わず、系統的にもれなく、バランスよく整理しよう”という姿勢に惹かれたのだと思います。
→ 中身をじっくり読むことによって、“ものごとの本質が、もれなく(バランスよく)系統的に整理されている”という特徴を知り、ますます『7つの習慣』に惹かれました。
◎ そして、この作品は、その後、筆者にとって、乗り越えなくてはならない大きな壁みたいな存在の1つとして、筆者に影響を与え続けてきたように思います。
→その後、この『7つの習慣』は、乗り越えなくてはならない大きな壁みたいな存在の1つとして筆者に影響を与え続けたように思います。
◎ かくして、現在、『7つのコンパス』のおかげで『7つの習慣』がよく理解できる── &『7つの習慣』のおかげで『7つのコンパス』がよく理解できる── というシナジー関係も生まれてきたのだと思います。
(“参考文献2”の典型的な例たる所以の1つです)
→
かくして、現在、『7つのパラダイム』のおかげで『7つの習慣』がよく理解できる &『7つの習慣』のおかげで『7つのパラダイム』がよく理解できる── そのようなシナジー関係が成立しているのだと思います。
※“参考文献2”の典型的な例たる所以の1つです。
◎ (そのようなことをしたら自分をなくしてしまうと思います)
→ ※そのようなことをしたら自分をなくしてしまうと思います。
◎認識してきています。
→認識しています。
◎ (例えば、“コンパス”に対する理解の仕方──コンパスの比喩づけのしかた、原則って結局何?…、等々)
→※例えば、“コンパス”の解釈や比喩づけ方、原則(principles)って結局何?…、等々。
◎ しかし、 本質的な部分では、『7つのコンパス』が、『7つの習慣』と深く調和していてほしいと感じますし、実際に調和していると信じています。
後々、原文を読む機会があり、その思いは、より確信に近くなりました。また、コヴィー先生を、より深く、より身近に理解できたように感じました。
(be in harmony with〜という英語表現があることを原著で初めて知りました。
I believe that 7Cs are in harmony with 7Hs.)
→ しかし、 本質的な部分では、『7つのパラダイム』が『7つの習慣』と深く調和していると考えています。
※be in harmony with〜という英語表現があることを原著で初めて知りました。
I think The 7 Paradigms are in harmony with The 7 Habbits.
◎7C分析→7P分(7つのパラダイム分析)
◎・結局、原則とは、なんのこと?
──“For Life”のことじゃないのか?
→・結局、原則(principles)とは、何のこと?
──“For Life”のことではないでしょうか?
◎ 本書に挙げられてる原則の例── courage、service、fairness、integrity、honesty、human dignity、quality、excellence、potential、growth、patience、nurturance、encouragement、1-7の原則… それ自体で“For Life”と調和しているものと、“For Life”と調和してはじめて本物になるものがあるのではないでしょうか?
→ 本書に挙げられている原則(principles)の例── courage、service、fairness、integrity、honesty、human dignity、quality、excellence、potential、growth、patience、nurturance、encouragement、1-7の原則(principles)… それ自体で“For Life”路線であるものと、“For Life”路線あってはじめて本物になるものがあるのではないでしょうか?
◎ ・パラダイムとは、“プチ・マップ”と解釈
→・『7つの習慣』に登場するパラダイムは、「原理的思考(principled thinking)の実践」の成果と解釈
※『7つのパラダイム』のパラダイムは、いわばメタ・パラダイムに相当
◎・習慣とは、“人生レベル”→“細胞の社会レベル”という自動化のようなものの一例
→・習慣とは、“人間レベル”→“細胞社会レベル”の自動化の所産の一例
◎・“4つの側面”について。
精神的← →肉体的 『In Out』上のもの。
知性← →情緒は、『カラダ アタマ』上のもの。
“社会”は、人間社会レベル “知性&情緒”は、人生レベル──
→・“4つの側面”について。
精神的 肉体的 ──『In Out』上のもの
情緒 知性 ──『カラダ アタマ』上のもの
“社会”が人間社会レベルだとすれば、“知性&情緒”は人間レベル
◎ ・「反応性のモデル 主体性のモデル」は、『人生レベル』の3 Steps(7番目のコンパス)における、detour の有無に対応
→・「反応性のモデル 主体性のモデル」 ──反応性のモデルが細胞社会レベルだすれば、主体性のモデルは人間レベル
◎・成長の螺旋について
学び→決意→実行→ の繰り返しも、『人生レベル』の3 Steps理論(7番目のコンパス)と調和。人生レベルで、それぞれの部分がdetourに なっている。
→・成長の螺旋について
学び→決意→実行→ の繰り返しも、人間レベルの3ステップス(7番目のパラダイム)と調和。人間レベルで、それぞれの部分がdetourに なっている。
◎・1、2、3の習慣は、実は、『人生レベル』の3 Stepsに、おおよそ対応している。
→・第1、第2、第3の習慣のそれぞれは、おおよそ、人間レベルの3つのステップスに対応している。
◎コヴィー先生と筆者の違いは、コヴィー先生の人生の歴史と、筆者の人生の歴史が違うからこそ生じるものだと思います。
→コヴィー先生と筆者の違いは、コヴィー先生と筆者の「人生の種、咲く花、実る果実」が違うからこそ生じているのだと思います。
◎ そして、それぞれの歴史の所産──“コヴィーフルーツ”と“さんぽフルーツ”が異なるからこそ、シナジーが生まれうる──。
→ そして、“コヴィーフルーツ”と“さんぽフルーツ”が異なるからこそ、シナジーが生まれうる──。
◎この本、そして、コヴィー先生との出会いは、とても、フルーツフルな貴重な出会いであったと信じています。
→『7つの習慣』&コヴィー先生との出会いは、とても貴重でフルーツフルな出会いでした。
『パラダイム・ブック』
◎
それは、中古本屋さんをめぐっている時だった。
→ それは、ある中古本屋さんの店内をめぐっていたときだった。
◎中を見ると、充実していて、意欲的で、興味深い内容の本であることがすぐわかった。読むべき本だと確信し、購入することに決めた。
→ さらっと中を見ると、充実していて意欲的な本でありそうなことがわかった。
古かったので、あまり期待していなかったが、価格が手頃だったこともあり、お試し的に購入しておくことにした。
◎ なぜ、その本に魅かれて、手に取ったのでしょうか?
それは、“パラダイム”というキーワードが、ホットに頭の中にあったのが大きいと思います。
→ そもそも、なぜ、その本を手に取ったのでしょうか?
それは、“パラダイム”というキーワードが、ホットに頭の中にあったことが大きかったと思います。
◎2012年5月3日のバージョンアップの頃から、 『7つのコンパス』の物語で“パラダイム”なる表現を取り入れ始めました。
→ 2012年5月のバージョンアップの頃から、物語 『7つのコンパス』(『7つのパラダイム』の前身)におけるプチ・マップの説明として“パラダイム”なる表現を取り入れ始めました。
◎ それまでの、“道しるべ”に、どうも、不満が募ったため、別の表現を探し── それで、たどり着いた表現が“パラダイム”でした。 → それまでの“道しるべ”がプチ・マップの説明にふさわくないことが次第に明確になり、別の表現を探した結果たどり着いた表現が“パラダイム”でした。
◎ そして、そのバージョンアップをしてから、しばらくたったある日に、この本と出会ったのでした。 “出会ってしまった──” と言えるほど衝撃的な出会いでした。
→ そして、そのバージョンアップから、しばらくたったある日に、この本と出会ったのでした。
◎ さっそく、パラダイム・ブックについても“7C分析&3Steps検証読み”をしました。
→ 購入後しばらくして、この本をじっくり読みました。
その際、さっそくパラダイム・ブックについても“7C分析(7つのコンパス分析、7P分析(7つのパラダイム分析)の前身)&3ステップス検証読み”をしてみました。
◎例によって、すべてを鵜呑みにした訳ではなかったのですが── 筆者は、本書の一部、主に“生命編”と、“精神編”の中にあった『グローバル・ブレイン』に触れた項目の一部に、衝撃を受けました。
→ 例によって、すべてを鵜呑みにした訳ではなかったのですが、筆者は、この本の「“生命編”の多くの部分」と「“精神編”の中にあった『グローバル・ブレイン』に触れた項目の一部」に、衝撃を受けました。
◎ 自分の不勉強、無知… を思い知らされました。
一方で、それらが、7C(7つのコンパス、特に1stや7th)や、3S(3Steps理論)と、よく調和していると感じることで── 大いなる味方、応援団を得たような気持ちにもなりました。
そして、それぞれの著書を読みたくなりました。 読むべきだと思いました。
→
『パラダイム・ブック』との出会いは、“出会ってしまった” と言えるほど、当時の筆者にとって衝撃的であることが判明しました。
なぜ衝撃だったのかといえば、それらが『7つのコンパス』(『7つのパラダイム』の前身、特に1stや7th)や、3ステップス哲学と驚くほどよく調和していたからです。
※今から思えば、喜びが先行してもよかったのだと思います。
しかし、当時の筆者の未熟さが、衝撃を先行させたのだと思います。
自分の不勉強、無知… を思い知らされた筆者は、それぞれの著書を読んで、詳しく学ぶべきだと思いました。
◎追加
それでも、やはり、決して、『パラダイム・ブック』のすべてを鵜呑みにしているわけではありません。
ところどころ違和感を持ち続けております。
※例えば、自然(nature)と調和している真実が“ある極めて特殊な精神状態でないとたどり着けない”とは、どうしても思えません。疲れていても、へこんでいても、元気なときも、うれしいときも、悲しいときも、楽しいときも… どんなコンディションであろうと関係なくたどり着ける真実こそが、自然(nature)と調和している真実の候補であると、筆者は思います。
やはり、ある本の中の部分部分にも、それぞれに相性があるのだと思います。
なお、筆者は、のちに(マイ・ブックサーフィン『人間性の心理学』のページが9割以上できていた頃)『パラダイム・ブック』の中に、『4“第三勢力”マズローの人間性心理学』の項目があったことに気づき、驚きました。
なぜ、すっかり素通りしてしまっていたのでしょうか?
それは、『パラダイム・ブック』の中では、違和感(いかがわしさ、怪しさ、アブナさ…)をもたらす「変性意識、ドラッグ(LSD)、トランスパーソナル心理学、第四の心理学、意識の進化(霊的段階…)、神秘主義… 」への流れの歯車(源流)として『“第三勢力”マズローの人間性心理学』が紹介されてしまっていたからだと思います。(誤解を招きうるように思われ、残念でなりません)
やはり、自己実現者が本来『愛他的で、献身的で、自己超越的、社会的である』という経験的事実が十分に尊重されさえすれば、本来、「第四勢力としてトランスパーソナル心理学」が不要になると筆者は思います。詳細な検討は、今後の課題です。
しかし、『パラダイム・ブック』と出会いは、やはり本格的なブックサーフィンのきっかけになったという意味で貴重でした。
さらには、のちに読んだ物質編の中で「EPRの実験、量子論、アインシュタイン…」というキーワードや人物に出会えたおかげで、「量子力学についての本、相対性理論についての本を読んでみよう」という気持ちが育まれたことを考え合わせると、やはり『パラダイム・ブック』はすごい本だと思います。
心から感謝いたしております。
◎該当部分 3Steps→3ステップス
◎少なくとも、その目的〈科学の統一を目指す〉、哲学が、3ステップス理論と調和していると思います。
→少なくとも、その目的〈科学の統一を目指す目的〉が、3ステップス哲学と調和していると思います。
◎該当部分 理論→哲学
◎3ステップスの進化と調和していると思いました。→3ステップスの進化と調和しています。
◎ホロンの概念は、3ステップス哲学と調和していると思います。
→ホロンの概念は、3ステップス哲学と調和しています。
◎3ステップス哲学でのレベルの違いを示しています。 両者の違いが、ここにあると思います。
→3ステップス哲学でのレベルの違いを示していますので、両者は違います。
◎該当部分 文字サイズを小さくする。
◎ つまり、両者は、表現しようとする現実はおおよそ同じでも、表現の仕方〈強調点〉が多少違うと言うことです。 そして、違うからこそシナジーが生まれうる──。
3ステップスのおかげで、この本の理解が深まり、この本のおかげで、3ステップス哲学への理解が深まっています。
→ つまり、両者は、表現しようとする現実はおおよそ同じでも、表現の仕方〈強調点〉が多少違うのだと思います。
3ステップス哲学のおかげで、この本の理解が深まり、この本のおかげで、3ステップス哲学への理解が深まるところがあると思います。
◎そして、その本の始めの方を読み、→ 当時、その本の始めの方を読み、
◎そして、その中の「デイジー理論」は、→その中の「デイジー理論」は、
◎「(地球システムの一部である)生態系が生きている」という意味を含むからだと思います。
→「(地球システムの一部である)生態系が本当に生きている」からだと思います。
◎ いろいろ変化しうるので──。→いろいろ変化しうるからです。
◎ でも、生態系における『カラダ アタマ』の意味付け方に、少し自信がなかったので、その点について勇気づけられました。
→それでも、生態系における『カラダ アタマ』の意味付け方に、少し自信がありませんでしたので、その点について勇気づけられました。
◎ 3ステップスの進化と調和していると思います。→ 3ステップスの進化と調和していると思いました。
◎削除
※『パラダイム・ブック』&上記の個々の本の中のすべてを鵜呑みにしている(受け入れている、支持している…)訳ではありません。 申し訳ないですが── 少なくとも科学的な見方をするならば、部分的には、きっぱりと拒絶せざるをえません。
(例えば、『パラダイム・ブック』の意識編の中の、“グローバル・ブレイン”以外のほとんどの部分── &“グローバル・ブレイン”に触れた部分の中の一部 ──。 プロローグの一部、物質編&生命編の中の一部──。 …
科学的な真実が、“ある極めて特殊な精神状態でないとたどり着けない”とはどうしても思えません。 疲れていても、へこんでいても、元気なときも、うれしい時も、悲しいときも、楽しいときも… どんなコンディションであろうと関係なく、たどり着けるものこそが、科学的な真実の候補であると、筆者は思います。)
やはり、ある本の中の部分部分にも、それぞれに相性があるのだと思います。
しかし、人生的な見方をするならば── 「 積極的に“支持する”ことはできないけれど、きっぱり“拒絶する”することもできない」といった一面もあるように思われます。 なぜなら、“人生”の多様性、“文化”の多様性… は、やはり、ある程度、尊重されるべきだと思うからです。
また──
後に、この本の物質編を通じて、EPRの実験、量子論、アインシュタイン… というキーワードや人に出会ったおかげで、のちに、量子力学についての本、相対性理論についての本を読んでみよう、という気持ちが育ったことを考えると、やはり、『パラダイム・ブック』は、すごい本だと思います。
心から感謝いたしております。
『imidas1992』
◎該当部分 空白の修正
◎その中で、“勉強に取り組むための、やる気、モチベーション…”を維持することは、とても大切なことであった。
そのような状況の中で── 本屋さんで、この『imidas(イミダス)1992』を見つけた。
→当時、“勉強に取り組むための、やる気、モチベーション…”を維持することを大事にしていた。
ある日、本屋さんで、この『imidas(イミダス)1992』を見つけた。
→ある日、本屋さんで『imidas(イミダス)1992』(集英社)を見つけた。
◎ 興味本位で、手にとり、中身を見てみた。
→ 興味本位で手にとり、中身を見た。
◎ しばらく、あれこれ思いめぐらせた結果──
筆者は、購入を決意した。
→ しばらく、あれこれ思いめぐらせた結果、筆者は購入を決意した。
◎ 受験生時代から、「将来、研究をやりたい」という気持ちが強くありました。
“その研究の夢を実現するために、受験勉強をしているのだ”と自分に言い聞かせながら、受験勉強を動機付けていました。
→ 受験生時代には、高3のときから(湯川秀樹の『旅人』に影響されて以来)育まれていた「将来、学問をやりたい気持ち」がありました。
一方で、「将来の学門のための勉強」と「目の前の現実の受験勉強」の間には大きなギャップがありました。
このギャップを乗り越えたかった(カバーしたかった)のだと思います。
◎ この本、『imidas(イミダス)1992』(集英社)を書店で手にしたとき──
将来、本当に研究するんだったなら、この本の内容は、いずれ、きっと必要となるだろうし、きっと役立つだろう。
たっぷり情報がつまっていて、コストパフォーマンスも高そうだ。
目指す大学にはいったら、ここに載っているような、最先端の面白そうな内容についての勉強も、思う存分できるぞ。
…
と思いめぐらせたのだろうと思います。
→ この本、『imidas(イミダス)1992』(集英社)を書店で手にしたとき──
「将来、本当に学問するなら、この本の内容も、いずれ、きっと必要となるだろうし、きっと役立つだろう。
たっぷり情報がつまっていて、コストパフォーマンスも高そうだ。大学に合格したら、ここに載っているような最先端の面白そうな内容についての勉強も思う存分できるぞ。…」のように思いめぐらせたのだと思います。
◎ つまり、わが研究志向性のシンボルとして、将来叶えたい夢の象徴として、大学に入ってからのお楽しみとして── 研究へのモチベーション、自分のアイデンティティー… を支える続けるために、筆者は、この『imidas(イミダス)1992』を購入したのだと思います。
→ つまり、わが学問志向性のシンボルとして、将来叶えたい夢の象徴として、大学に入ってからのお楽しみとして── 学問へのモチベーション、自分のアイデンティティー… を支える続けるために、筆者は、この『imidas(イミダス)1992』を購入したのだと思います。
◎そうやって、受験時代を乗り越えるための力(自分自身の心のバランスをとるための支え)の1つにしようとしたのだと思います。
→そうやって、受験勉強によって自分を見失わないための支えの1つにしようとしたのだと思います。
◎ 確かに、たとえ 受験勉強の内容とはほとんど接点がなく、時間が貴重であった受験生時代に開くことはほとんどなかった『imidas(イミダス)1992』でありましたが──
→ 確かに、たとえ 受験勉強の内容とはほとんど接点がなく、時間が貴重であった受験生時代に開くことがほとんどなかった『imidas(イミダス)1992』でありましたが──
◎追加※「単位や資格をとるための勉強」の合間では── ライフサイエンスに惹かれたことで自然にやっていたライフサイエンス系の勉強(『細胞の分子生物学 第二版』、『Oh! 生きもの』、『ストレスと免疫』…)や、人生における「悩み、葛藤、不安…」があったことで自然にやっていた人生系の勉強(『人間性の心理学』、『7つの習慣』…)が限界だったのだと思います。
◎ そして、2000年に、ついに、「“研究&執筆”に専念する」という大決断を果たし、あの、経済的に切り詰めた生活をスタートさせてから間もなくのことでした(2000年9月〜)。
→ そして、ついに“学問&執筆”に専念するという大決断を果たし、経済的に切り詰めたあの生活(参考 エッセイ『時間』)をスタートさせてから間もなくのことでした(2000年9月〜)。
◎ 念願の自由を手に入れて、「研究と執筆に専念すんぞ!」と、やる気や希望は大きかったのですが── 一方で、仕事もやめて、大学からも遠ざかっていたので、経済的&社会的な不安もありました。
→ 念願の自由を手に入れて、学問&執筆に向けた、やる気や希望は大きかったのですが── 一方で、仕事もやめて、大学からも遠ざかっていましたので、経済的&社会的な不安もありました。
◎ どんな気持ちで、この『imidas(イミダス)1992』のページをめくったのか?
おそらく、当時(2000年9月〜)から見ても、すでにだいぶ古くなっていたので、あまり期待しておらず、「とりあえず、これを読もう」みたいな軽い気持ちであったろうと思います。
→ どんな気持ちで、この『imidas(イミダス)1992』のページをめくったのでしょうか?
おそらく、当時(2000年9月〜)から見ても、すでにだいぶ古くなっていましたので、あまり期待しておらず、「とりあえず、これを読もう」みたいな軽い気持ちであったと思います。
◎ 92年頃から、ほとんど開くことがなかったけれど、ずっと本棚にあり、身近に感じていた『imidas(イミダス)1992』との、8年越しの再会は、筆者に、とてつもなく大きなものを与えて下さりました。
→ 92年頃から(ほとんど開くことがなくても)ずっと本棚にあり身近に感じていた『imidas(イミダス)1992』との8年越しの再会は、とてつもなく大きなものを筆者に与えてくださりました。
◎キーワードに出会ったのは。
→キーワードに出合ったのは──。
◎
『〜注目すべきことは、わずか三個の自由度をもつ力学系においてすでにカオスが可能だということである』
(『imidas(イミダス)1992』 集英社 p.735 下線は、筆者による) |
→
…注目すべきことは、わずか三個の自由度をもつ力学系においてすでにカオスが可能だということである。
(『imidas(イミダス)1992』 集英社 p.735) 下線は、筆者によります。 |
◎ (経済的に切り詰めていた状況なら、なぜ図書館ではなく、大型書店だったのかと不思議に思われる方もおられるかもしれません。
1つの理由は、「学ぶ(学習する)ための本は所有するものだ。学習参考書のように、専門書などの本の内容も、長く所有して、くり返し読んでこそ身に付くことができる」と考えていたからだと思います。
そして、もう1つの理由は、やはり、「研究をするためには、最新の本でなければならない。最新の本は、本屋さんにこそある」と考えていたからだと思います)
→※経済的に切り詰めていた状況なら、なぜ図書館ではなく、大型書店だったのかと不思議に思われる方もおられるかもしれません。
1つは、付属図書館のある大学から遠ざかってしまったことが大きいと思います。
もう1つは、「学ぶ(学習する)ための本は所有するものだ。学習参考書のように、専門書などの本の内容も、長く所有して、くり返し読んでこそ身に付くことができる」のように考えていたからだと思います。
そして、もう1つは、やはり、「最新の学問をするためには、最新の本でなければならない。最新の本は、本屋さんにこそある」のように考えていたからだと思います。
◎その本棚の中で、“研究に必要な本はどれだろう。学び、身につけるべき内容を持つ本はどれだろう”という思いを持ち、時間をかけて、あれこれ吟味させていただきました。
→その本棚で「必要な本はどれだろう。学ぶべき内容を持つ本はどれだろう」という気持ちで、時間をかけて、あれこれ吟味させていただきました。
◎ そして、その日、選びに選んで、購入を決めたものが、次の2冊でした。
『混沌からの秩序』(I.プリゴジン/I.スタンジェール 伏見康治・伏見譲・松枝秀明訳 みすず書房)
『複雑系入門 知のフロンティアへの冒険』(井庭崇 福原善久 NTT出版)
→ そのとき、選びに選んで購入を決めた本が、次の2冊でした。
『混沌からの秩序』(I.プリゴジン/I.スタンジェール 伏見康治・伏見譲・松枝秀明訳 みすず書房)
『複雑系入門 知のフロンティアへの冒険』(井庭崇 福原善久 NTT出版)
◎特に『混沌からの秩序』は、とても高価だったので、→特に『混沌からの秩序』は、とても高価でしたので、
◎ それほど、“根拠”に飢えていたのだと思います。
→ それほど“根拠”に飢えていたのだと思います。
◎ その理由は、書店の関連分野の本棚の中で、時間をかけて、あれこれ吟味させていただいた中で
『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』(田坂広志 講談社)
に出会っていたから、というのがとても大きかったのだと思います。
→ その書店の関連分野の本棚で、時間をかけて、あれこれ吟味させていただいた中で
『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』(田坂広志 講談社)
に出会っていたからだと思います。
◎ ──実は、まさに、このページ(『imidas(イミダス)1992』を起源とするブックサーフィンのページ)をまとめている途中で、『自己組織化の3つの条件』って、どこにあったっけ? ということが、筆者の中で大きな問題になりました。
→ ──実は、まさに、このページ(マイ・ブックサーフィン『imidas(イミダス)1992』のページ)をまとめている最中に、「『自己組織化の3つの条件』って、どこにあったっけ?」ということが、筆者の中で大きな問題となりました。
◎ その後、(記憶の中にあった)『自己組織化の3つの条件』の由来探しが始まりましたが、所持している本のどこを探しても見つからず、ネットで検索しても見つからず、しばらく途方に暮れました。
→記憶の中をたどっても、所持している本を探しても、ネットで検索しても『自己組織化の3つの条件』の由来が見つからず、しばらく途方に暮れました。
◎そして、その後、もしかしたら、あの日、本選びをしているときに出会った“あの本”の中にあった? というような感じで、ぼんやりと本のイメージが心に浮かぶようになりました。
→その後、「もしかしたら、あの日、本選びをしているときに出会った“あの本”の中にあった?」のような感じで、ぼんやりと本のイメージが心に浮かぶようになりました。
◎ そして、「ぼんやりした表紙のイメージは浮かぶけれども、書籍名や著者名は、はっきり思い出せない」 そんなモヤモヤした日々がしばらく続いた後の、ある日のことです。
→ そして、「ぼんやりした表紙のイメージは浮かぶけれども、書籍名や著者名は、はっきり思い出せない」というようなモヤモヤした日々がしばらく続いた後のことです。
◎ 中古本屋さんで『複雑系の経営 「複雑系の知」から経営者への七つのメッセージ』(田坂広志 東洋経済)に出会いました。
→ 中古本屋さんで『複雑系の経営 「複雑系の知」から経営者への七つのメッセージ』(田坂広志 東洋経済)に出会ったのは──。
◎ 手に取ってページを開いてみると(『七つの』に魅かれたのだと思います)──
→ 手に取ってページを開いてみると(『七つの』に惹かれたのだと思います)、
◎ (具体的に、その3つの条件とは、“外部との開放性、非平衡な状態、ポジティブ・フィードバックの存在”の3つです)
→※具体的に、その3つの条件とは、“外部との開放性、非平衡な状態、ポジティブ・フィードバックの存在”の3つです。
◎ その後しばらくの間、この本こそが、探し求めていたミッシングリンクにちがいないと思い込んでしまいました。
→ その後しばらくの間、「この本こそが探し求めていたミッシングリンクにちがいない」と思い込んでしまいました。
◎ そもそも、“自己組織化の3つの条件”が、なぜ、それほど重要で、記憶に残っていたのか?
→ そもそも、なぜ、“自己組織化の3つの条件”が、それほど重要で記憶に残っていたのでしょうか?
◎(この“自己組織化の3つの条件”がきっかけとなり、“1つにまとめる← →それぞれにわける”が、非平衡・平衡(バランス、アンバランス)の意味を含む、『“on/off”』へと進化し、そして、3つの表現を統一させるべく、“外← →内”を『“in/out”』と表記することになりました)
→※この“自己組織化の3つの条件”がきっかけとなり、まず、“1つにまとめる← →それぞれにわける”が、(平衡・非平衡(バランス、非バランス)の意味を含む)『“on/off”』へと進化しました。そこから、3つの表現を統一させるべく、“外← →内”を『“in/out”』と表記することにしました。
◎ すなわち、自己組織化の3つの条件は、
第4の地図『“in/out”』
第5の地図『“for/against”』
第6の地図『“on/off”』
の“根拠”の1つに相当するものだったからです。
→ つまり、自己組織化の3つの条件は、
第4の地図『“in/out”』
第5の地図『“for/against”』
第6の地図『“on/off”』
の“根拠”の1つに相当していたからこそ、それほど重要で記憶に残っていたのです。
◎削除 (第4の地図『“in/out”』が「開放系かどうか(外部か内部か)」の意味を含み、第5の地図『“for/against”』が「ポジティブ・フィードバックかネガティブ・フィードバックか」の意味を含み、第6の地図『“on/off”』が「非平衡系か平衡系か」の意味を含むというように、より普遍性が高まったことは、自信を深める根拠の1つとなりました)
◎ 以上のような、第4の地図『“in/out”』、第5の地図『“for/against”』、第6の地図『“on/off”』への進化、および、その根拠の獲得は── 『7つの地図』が、単に人生を含むライフサイエンスだけでなく、自然科学とも調和した普遍的なものになるための、重要なステップの1つであったのは間違いないと思います。
→ 以上のような、第4の地図『“in/out”』、第5の地図『“for/against”』、第6の地図『“on/off”』への進化、および、その根拠の獲得は、『7つの地図』(『7つのパラダイム』の前々身)が(単に人生を含むライフサイエンスのみならず)自然科学全般と調和した普遍的なものになるための重要なステップの1つであったのは間違いないと思います。
◎※なお、今から、見れば、“非平衡系”は、(単なる『Off』ではなく)「『For』>『Against』に相当する『Off』」を意味し、“ポジティブ・フィードバック”は、「『For』の方向の3Steps」を意味するという解釈の方が、より正確なようです。
→※なお、今から見れば、“非平衡系”は、(単なる『Off』ではなく)「『For』>『Against』に相当する『Off』」を意味し、“ポジティブ・フィードバック”は、「『For』の方向の3ステップス」を意味するという解釈の方が、より正確なようです。
◎しかし、その後── あの日、本当に、“経営者のための本”が、あのときの書店の科学書の本棚にあったのだろうか? と疑問が浮かぶようになりました。
→しかし、その後、「あの日、“経営者のための本”が、あのときの書店のあの本棚に本当にあったのだろうか?」と疑問が浮かぶようになりました。
◎ そんなある日、ネットで、田坂広志氏の著作を調べていたところ、『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』の表紙に、“見たことあるような感じ”(既視感)を持ちました。もしかして── と思い、さっそく購入して調べてみると、まさに、この本の中にも、『自己組織化の3つの条件』がありました!
→ そんなある日、ネットで田坂広志氏の著作を調べていたところ、『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』(田坂広志 講談社)の表紙に“見たことあるような感じ”(既視感)を持ちました。「もしかしてこれじゃないか?」と思い、さっそく購入して調べてみると、まさに、この本の中にも『自己組織化の3つの条件』がありました!
◎
『プリゴジンは、こうした現象を研究することによって、自己組織化が生じるためには三つの条件が必要であることを明らかにしました。その三つの条件とは、「オープン」(開放系)であること、「ダイナミック」(非平衡系)であること、「ポジティブ・フィードバック」(自己加速系)が存在することの三つである。』
(『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』 p86 第三章『創発の三つの条件』 下線は、筆者による) |
→
プリゴジンは、こうした現象を研究することによって、自己組織化が生じるためには三つの条件が必要であることを明らかにしました。その三つの条件とは、「オープン」(開放系)であること、「ダイナミック」(非平衡系)であること、「ポジティブ・フィードバック」(自己加速系)が存在することの三つである。
(『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』(田坂広志 講談社)p86 第三章『創発の三つの条件』) 下線は筆者によります。 |
◎ (なお、「非平衡系」のみならず、「ダイナミック」も、『On Off』への進化を促したと思われます)
→※ここに至り、「非平衡系」のみならず「ダイナミック」も『On Off』への進化を促していたことを思い出しました。
◎この本こそ、探し求めていたミッシングリンクに間違いないと思います。
→この本こそ、探し求めていたミッシングリンクに間違いないありません。
◎ そして、当時、『imidas1992』の中で、『自己組織化』、『非平衡開放系』、『プリゴジーヌ』、『3つの自由度でカオス』に出会っていたからこそ、本選びの日に、この『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』の中で、この“自己組織化の3つの条件(『創発の三つの条件』)”の部分に、ピンポイントで最も惹き付けられたのだと思います。
→当時、すでに『imidas1992』の中で『自己組織化』『非平衡開放系』『プリゴジーヌ』『3つの自由度でカオス』のキーワードに出合っていたからこそ、あの本選びの日に、『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』の中の“自己組織化の3つの条件(『創発の三つの条件』)”の部分にピンポイントで最も惹き付けられたのです。
◎ そして、この “自己組織化の3つの条件”(『創発の3つの条件』)の中の“開放系”が『“外← →内”(第4の地図)』と、“ポジティブ・フィードバック”が『“for← →against”(第5の地図)』と関連があるらしいことを、この本選びの最中に、すぐに察知できたのだと思います。
→ また、だからこそ、この “自己組織化の3つの条件”(『創発の三つの条件』)の中の“開放系”が『“外← →内”(第4の地図)』と、“ポジティブ・フィードバック”が『“for← →against”(第5の地図)』と関連しているらしいことを、この本選びの最中に、すぐに察知できたのです。
◎ そして、だからこそ、この“自己組織化の3つの条件(『創発の3つの条件』)”(byプリゴジン)こそが、当時、探し求めていた根拠として、とても重要であると確信したのだと思います。
→ また、だからこそ、この“自己組織化の3つの条件(『創発の三つの条件』)”(byプリゴジン)こそが、当時探し求めていた根拠として非常に重要であると確信したのです。
◎ そして──
プリゴジンの著作を読んで勉強すれば、“自己組織化の3つの条件”を詳しく学べるはずだ。そうすれば、“自己組織化の3つの条件”こそが、科学的な根拠として、本当にふさわしいかどうかを確認できるはずだ。 だから、プリゴジンの著作を読むべきだ。 と考えたのだと思います。
→ その結果、「プリゴジンの著作を読んで勉強すれば、“自己組織化の3つの条件”を詳しく学べるはずだ。そうすれば、“自己組織化の3つの条件”こそが、科学的な根拠として、本当にふさわしいかどうかを確認できるはずだ。だから、プリゴジンの著作を読むべきだ」という考えに至ったのです。
◎ それが── かなり難しそうで、かなり高価であったのにかかわらず、相当無理して、
『混沌からの秩序』(I.プリゴジン/I.スタンジェール 伏見康治・伏見譲・松枝秀明訳 みすず書房)
を購入した大きな理由だったのだと思います。
→ 以上が、かなり難しそうで、かなり高価であったのにかかわらず、相当無理して、
『混沌からの秩序』(I.プリゴジン/I.スタンジェール 伏見康治・伏見譲・松枝秀明訳 みすず書房)
を購入した大きな理由です。
◎ つまり、『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』(田坂広志 講談社)が、『混沌からの秩序』(I.プリゴジン/I.スタンジェール 伏見康治・伏見譲・松枝秀明訳 みすず書房)を、かなり無理して購入する背中を押して下さる形になっていたのです。
→ つまり、『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』(田坂広志 講談社)が、『混沌からの秩序』(I.プリゴジン/I.スタンジェール 伏見康治・伏見譲・松枝秀明訳 みすず書房)を、かなり無理して購入する背中を押してくださっていたのです。
◎ 一方、『複雑系入門 知のフロンティアへの冒険』(井庭崇 福原善久 NTT出版)を購入することに決めたのは、なぜでしょうか?
→ 一方、『複雑系入門 知のフロンティアへの冒険』(井庭崇 福原善久 NTT出版)の購入を決めた理由は、何だったのでしょうか?
◎(“複雑系入門”は、それまでの無知な筆者なら、絶対に読まなかったような本のタイトルであったはずです。
(ちなみに、『imidas1992』には、“複雑系”という言葉は載っていません))
→※『複雑系入門』は、それまでの無知な筆者なら、絶対に読まなかったような本のタイトルであったはずです。なお、『imidas1992』には“複雑系”という言葉は載っていません。
◎ その理由は── 少なくとも次の3つあったと思います。
→ その理由は、少なくとも3つありました。
◎ 1つは、やはり、この『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』が、“複雑系”について、基礎から詳しく学ぶべきだ── という気持ちをおおいに高めてくれたからです。
→
1つは、やはり、この『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』が「“複雑系”について、基礎から詳しく学ぶべきだ」という気持ちをおおいに高めてくださったからです。
◎つまり、『複雑系入門 知のフロンティアへの冒険』についても、『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』が、背中を押して下さる形になっていたことになります。
→ つまり、『複雑系入門 知のフロンティアへの冒険』の購入についても、『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』が、背中を押してくださっていたことになります。
◎ もう1つの理由は、本の中に、リンゴの図があったことです。“創発”という概念を、一発で(直観的に)伝えようとする、その図に親しみを覚えました。
→ もう1つの理由は、本の中にリンゴの図があったことです。
“創発”という概念を一発で(直観的に)伝えようとする、その図に親しみを覚えました。
◎ そして、もう1つの理由は、世界についての“階層構造”の図があったことです。
それは、“複雑系の科学”という分野が解決しようとしている問題を、“一発で読み取れる図”でもありました。(「一図は、百言にしかず」の例であると思います)
→ そして、もう1つの理由は、世界全体を示す“階層構造”の図があったことです。
それは、“複雑系の科学”の課題が“一発で読み取れる図”でもありました。
※「一図は、百言にしかず」の例であると思います。
◎ (後に、その問題、すなわち、「“さまざまな分野の間のギャップを埋め、さまざまな分野をつなぐ”という、“複雑系の科学”が解決を目指している問題」の解決のために、もしかしたら、筆者も貢献ができるかも知れないと思うに至りました。
拙論文『3Steps理論とその応用について』(&『一般3Steps理論と“複雑系の科学”について』)には、“『複雑系』の科学”が解決を目指している問題に対して、1つの答えを与えている可能性がある、という一面もあると思います。
一方、この『複雑系入門 知のフロンティアへの冒険』のおかげで、“一発で読み取れる図”で明確に示されることに魅力を感じる── という経験ができたと言えるかもしれません)
→※後に、“複雑系の科学”の課題、すなわち、「さまざまな分野の間のギャップを埋め、さまざまな分野をつなぐという課題」の解決のために、筆者も貢献できるかもしれないと思うに至りました(拙論文『物質やライフの生成過程が持っているフラクタル構造』や『要素還元主義の成果を包含する“複雑系の科学”の本質』には、“複雑系の科学”の課題に対して、答えの1つを提供しているという一面もあると思います)。
一方、この『複雑系入門 知のフロンティアへの冒険』のおかげで、“一発で読み取れる図”で明確に示されることに魅力を感じるという経験ができたのだと思います。
◎ これらの理由で購入した『複雑系入門 知のフロンティアへの冒険』は、“複雑系”についてのさまざまな知識を0から教えて下さったのみならず、(下のテーブルに示すように)さらなるマイ・ブックサーフィンが展開されるための、“ハブ本”としても、貴重な働きをして下さりました。
→ これらの理由で購入した『複雑系入門 知のフロンティアへの冒険』は、“複雑系”についてのさまざまな知識を0から教えてくださったのみならず、(下のテーブルに示すように)さらなるマイ・ブックサーフィンが展開されるための、“ハブ本”としても、貴重な働きをしてくださりました。
◎ とくに、この本のおかげで、“フラクタル”の具体例である「“コッホ曲線”の図」と初めて出会えたこと、そして、このことがフラクタルについて詳しく学び始めるきっかけになったことは重要でした。
→ とくに、この本が、“フラクタル”の具体例である「“コッホ曲線”の図」と初めて出合わせてくださったこと、および、フラクタルについて詳しく学び始めるきっかけになったことは重要でした。
◎ なぜなら、フラクタルの一種である“コッホ曲線”がヒントとなり、単なる『焦点をあてる 価値付ける 動かす』というような3つの言葉による表記から、
という図を伴った表記へと進化することができたからです。
→ なぜなら、フラクタルの一種である“コッホ曲線”がヒントとなり、単なる『焦点をあてる 価値付ける 動かす』のような3つの言葉による表記から、
◎ こういった進化も、『7つの地図』が、単に人生だけと調和したものではなく、自然科学とも調和した普遍的なものになるための、重要なステップの1つであったのは間違いないと思います。
→ このような進化も、『7つの地図』(『7つのパラダイム』の前々身)が(単に人生と調和しているだけではなく)自然科学全体と調和している普遍的な“メタ・パラダイム”になるための重要なステップの1つであったのは間違いないと思います。
◎他の2つの本の購入する際の背中を押して下さりました。
→他の2つの本の購入する際の背中を押してくださりました。
◎結局、筆者は購入しませんでした(購入できませんでした)。
なぜか?
→結局、筆者は購入しませんでした。
なぜでしょうか?
◎感じとることができなかったからだと思います。
すなわち、『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』は、「当時の自分にとって、“先を行き過ぎた本”」であったのだと思います。 それは、「当時の自分には、この本を読みこなす器がなかった」とも言えると思います。
→感じとることができなかったからです。
それは、すなわち、「『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』が、当時の自分にとって“先を行き過ぎた本”であった」から、「当時の自分には、『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』を読みこなす器がなかった」からです。
◎ そして、だからこそ、“複雑系”についての基礎的な本こそを、厳選して購入すべきだと考えたのだと思います。
→だからこそ、“複雑系”についての基礎的な本こそを厳選して購入すべきだと考えたのだと思います。
◎そして、もう1つは、やはり、“購入できなかった”からだと思います。すなわち、経済的に切り詰めていた時期だったので、『混沌からの秩序』と『複雑系入門 知のフロンティアへの冒険』の2冊だけの購入が限界だったのだと思います。
→もう1つは、やはり、“購入できなかった”からだと思います。すなわち、経済的に切り詰めていた時期でしたので、『混沌からの秩序』と『複雑系入門 知のフロンティアへの冒険』の2冊だけの購入が限界だったのだと思います。
◎ 近年(2015年4月〜)、この『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』&『複雑系の経営 「複雑系の知」から経営者への七つのメッセージ』を、じっくり読ませて頂きました。
→ 2015年4月頃に、『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』&『複雑系の経営 「複雑系の知」から経営者への七つのメッセージ』を、じっくり読みました。
◎『このように、「個」が一定の規則にもとづいて「自発的」に活動するだけで、「全体」が自然に秩序や構造を形成するという特性を、「複雑系の知」においては「創発性」と呼んでいる。この特性は、第一章「全体性の知」において述べた「複雑化すると新しい性質を獲得する」という特性の別な側面でもある。』
(p51〜 『複雑系の経営 「複雑系の知」から経営者への七つのメッセージ』)
→
このように、「個」が一定の規則にもとづいて「自発的」に活動するだけで、「全体」が自然に秩序や構造を形成するという特性を、「複雑系の知」においては「創発性」と呼んでいる。この特性は、第一章「全体性の知」において述べた「複雑化すると新しい性質を獲得する」という特性の別な側面でもある。
(p51〜 『複雑系の経営 「複雑系の知」から経営者への七つのメッセージ』)
◎ さらに、筆者が親近感を持つ言葉、あるいは、共感する言葉、が、これらの本たちの中にありました。
→ さらに、親近感を持つ&共感する言葉が、これらの本たちの中にありました。
◎ 『〜物質、生命、人間、社会のそれぞれは、世界の進化という観点からは、明らかに異なった進化の段階にある。最初に、そのことを理解しなければならない。なぜならば、それぞれの進化の段階においては、まったく異なった法則が支配しているからである。さらにつけ加えるならば、これらの法則という言葉の意味も、物質、生命、人間、社会のそれぞれにおいて、異なってくるからである』
(p.147 『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』)
『すなわち、我々の生きる、この宇宙、地球、自然、社会、市場、企業などの世界は、常に複雑化し、自己組織化し、創発的に新しい性質を獲得し、それまでとは異なった世界へと進化し続けていく存在なのである』
(p.183 『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』)
→
…物質、生命、人間、社会のそれぞれは、世界の進化という観点からは、明らかに異なった進化の段階にある。最初に、そのことを理解しなければならない。なぜならば、それぞれの進化の段階においては、まったく異なった法則が支配しているからである。さらにつけ加えるならば、これらの法則という言葉の意味も、物質、生命、人間、社会のそれぞれにおいて、異なってくるからである。(p.147 『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』)
すなわち、我々の生きる、この宇宙、地球、自然、社会、市場、企業などの世界は、常に複雑化し、自己組織化し、創発的に新しい性質を獲得し、それまでとは異なった世界へと進化し続けていく存在なのである。(p.183 『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』)
◎
|
『〜厳密に言えば、我々が生きる、この宇宙、地球、自然、社会、市場、企業、という「世界」のすべてが、「複雑系」なのである。
我々が「世界」を「単純系」と「複雑系」に分類するのは、単なる便宜に過ぎない。これらの分類は、世界が、原理的に、この二つに分類されることを意味しているわけではない。正確に言えば、ある「時間スケール」と「空間スケール」において、その対象が、「単純系」として扱っても大きな問題を生じない場合に、これを便宜的に「単純系」と呼び、要素還元主義的な手法によって扱っているだけなのである。この点も、しばしば誤った解釈が流布されていることなので、敢えて指摘しておきたい。』
(p149 『複雑系の経営 「複雑系の知」から経営者への七つのメッセージ』)
『換言すれば、要素還元主義における世界認識の方法の欠点は、世界をロゴスにより二元論的に分割し、整理していくことである。こうした世界認識は、必然的に、二項対立を生み出し、世界に関する一面的な見方と価値観の対立を生み出してしまう。
これに対して、「コスモロジー原理」にもとづく世界認識の方法は、ロゴスによって二元論的かつ二項対立的に分割された要素のうち、一方を絶対化し、他方を排除することなく、相対立するように見える要素の双方を、一つの「コスモロジー」(意味の宇宙)の中に同時に受容・包摂してゆく方法である。
こうした方法を採ることにより、分割された要素どうしが、互いに一方の深層を照らし出し、相対立するように見える要素の間に、さらに深いレベルでの統一が存在することが浮かび上がってくる。』
(p.196 『複雑系の経営 「複雑系の知」から経営者への七つのメッセージ』)
『世界の本質は、決して線形や非線形という単純な言葉で表されるものではない。複雑きわまりない世界を、無理矢理に単純な数学モデルに押し込み、強引に方程式で表したとき、それがたまたま線形であったり、非線形であったりするに過ぎないのである。〜
我々の生きる世界のうち、数学モデルで表される世界は、ごくごく限られた領域にすぎず、そのうち、線形方程式で表される世界など、広大な砂漠の一握の砂ほどのものなのである。』(176〜178 『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』)
…
|
→
|
…厳密に言えば、我々が生きる、この宇宙、地球、自然、社会、市場、企業、という「世界」のすべてが、「複雑系」なのである。
我々が「世界」を「単純系」と「複雑系」に分類するのは、単なる便宜に過ぎない。これらの分類は、世界が、原理的に、この二つに分類されることを意味しているわけではない。正確に言えば、ある「時間スケール」と「空間スケール」において、その対象が、「単純系」として扱っても大きな問題を生じない場合に、これを便宜的に「単純系」と呼び、要素還元主義的な手法によって扱っているだけなのである。この点も、しばしば誤った解釈が流布されていることなので、敢えて指摘しておきたい。
(p149 『複雑系の経営 「複雑系の知」から経営者への七つのメッセージ』)
換言すれば、要素還元主義における世界認識の方法の欠点は、世界をロゴスにより二元論的に分割し、整理していくことである。こうした世界認識は、必然的に、二項対立を生み出し、世界に関する一面的な見方と価値観の対立を生み出してしまう。
これに対して、「コスモロジー原理」にもとづく世界認識の方法は、ロゴスによって二元論的かつ二項対立的に分割された要素のうち、一方を絶対化し、他方を排除することなく、相対立するように見える要素の双方を、一つの「コスモロジー」(意味の宇宙)の中に同時に受容・包摂してゆく方法である。
こうした方法を採ることにより、分割された要素どうしが、互いに一方の深層を照らし出し、相対立するように見える要素の間に、さらに深いレベルでの統一が存在することが浮かび上がってくる。
(p.196 『複雑系の経営 「複雑系の知」から経営者への七つのメッセージ』)
世界の本質は、決して線形や非線形という単純な言葉で表されるものではない。複雑きわまりない世界を、無理矢理に単純な数学モデルに押し込み、強引に方程式で表したとき、それがたまたま線形であったり、非線形であったりするに過ぎないのである。…
我々の生きる世界のうち、数学モデルで表される世界は、ごくごく限られた領域にすぎず、そのうち、線形方程式で表される世界など、広大な砂漠の一握の砂ほどのものなのである。
(176〜178 『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』)
…
|
◎ とても響いたり、親しみを覚えたりしたのみならず── 新たな気づきを与えて下さりました。
→ とても響いたり、親しみを覚えたりしたのみならず、新たな気づきを与えてくださりました。
◎ (そして、今、貴重な“応援本”の1つであると感じます。
『“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)』や『一般3Steps理論』の研究についても、「間違ったことはしてないよ」と励ましてくれる本たちであると感じます)
→※今も、貴重な“応援本”の1つであると感じ、励まされます。
◎ 近年(2015年4月〜)これらの本をきっかけとした、田坂広志氏の著作に関する新たなブックサーフィンも展開されました。
→ 2015年4月頃から、これらの本をきっかけとした、田坂広志・ブックサーフィンも展開されました。
◎ 『未来を予見する「5つの法則」』 田坂広志 光文社
『成長するマネジャー 12の心得 なぜマネジメントが壁に突き当たるのか』 田坂広志 東洋経連
『これから市場戦略はどう変わるのか 異業種連合7つの戦略』 田坂広志 ダイヤモンド社
→ 『未来を予見する「5つの法則」』 田坂広志 光文社
『成長するマネジャー 12の心得 なぜマネジメントが壁に突き当たるのか』 田坂広志 東洋経連
『これから市場戦略はどう変わるのか 異業種連合7つの戦略』 田坂広志 ダイヤモンド社
◎ 一方、筆者は、これまで、プリゴジン氏自身の著作の中に、“自己組織化の3つの条件”と整理された形で記述されているのを見たことがありません。
→ 一方、筆者は、これまで、プリゴジン氏自身の著書の中に、“自己組織化の3つの条件”と整理された記述を見たことがありません。
◎※近年(2015年4月〜)、プリゴジン氏の著作も、読ませて頂きました。
→※2015年4月頃から、プリゴジン・ブックサーフィンも展開されました。
◎『散逸構造』 ニコリス プリゴジーヌ 小畠陽之助 相沢洋二訳 岩波書店
『複雑性の探求』 G・ニコリス/I・プリゴジン 我孫子誠也・北原和夫訳 みすず書房
『構造・安定性・ゆらぎ』 ─その熱力学的理論 グランドルフ/プリゴジン
松本元・竹山協三訳 みすず書房)
→
『散逸構造』 ニコリス プリゴジーヌ 小畠陽之助 相沢洋二訳 岩波書店
『複雑性の探求』 G・ニコリス/I・プリゴジン 我孫子誠也・北原和夫訳 みすず書房
『構造・安定性・ゆらぎ ─その熱力学的理論』 グランドルフ/プリゴジン 松本元・竹山協三訳 みすず書房
…
◎ ですので、 『創発の三つの条件』&『「自己組織化」の三つの条件』という表現(洞察、整理…)は、田坂広志氏のオリジナルのものなのだろうと思うに至っております。
→ ですので、 『創発の三つの条件』&『「自己組織化」の三つの条件』という表現(洞察、整理…)は、田坂広志氏のオリジナルなのだろうと思うに至りました。
◎ 筆者は、この本質的な洞察──『創発の三つの条件』&『「自己組織化」の三つの条件』のおかげで、新たなブックサーフィンを展開できたのみならず、『7つの地図』を進化させることもできました。
→ この本質的な洞察──『創発の三つの条件』&『「自己組織化」の三つの条件』のおかげで、筆者は、新たなブックサーフィンを展開できたのみならず、『7つの地図』(『7つのパラダイム』の前々身)を進化させることができました。
◎ そして、研究成果『3Steps理論と、その応用について』が、『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』や『複雑系の経営 「複雑系の知」から経営者への七つのメッセージ』の中に提示されている問題に対する、答えの1つになっているかもしれないことを思うとき──
「機械論的パラダイム」から「生命論的パラダイム」へと転換していく流れが、既存の理論物理学を包含する『“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)』が生まれる流れと調和していることに気づくとき──
田坂氏が引用された『我々は、「言葉」にて語り得るものを語り尽くしたとき、「言葉」にて語り得ないものを知ることがあるだろう』(byヴィトゲンシュタイン)という言葉と、『3Steps理論』が調和しているかもしれないと思うとき──
→
成果『物質やライフの生成過程が持っているフラクタル構造』や『要素還元主義の成果を包含する“複雑系の科学”の本質』が、『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』や『複雑系の経営 「複雑系の知」から経営者への七つのメッセージ』の中に提示されている課題に対する答えの1つになっているかもしれないと思うとき──
「機械論的パラダイム」から「生命論的パラダイム」へと転換していく流れが、従来の理論物理学を包含する『素スピノル物理学』が生まれる流れと調和していることに気づくとき──
田坂氏が引用なさった『我々は、「言葉」にて語り得るものを語り尽くしたとき、「言葉」にて語り得ないものを知ることがあるだろう』(byヴィトゲンシュタイン)と、「3ステップスのフラクタルの図」が調和しているかもしれないと思うとき──
◎ そして、その後、他にも、さらなる新たなブックサーフィンが展開されることになりました。
『生命論パラダイムの時代』
イリヤ・プリゴジン 浅田彰 立花隆 石垣通 西山賢一 松井孝典 田坂広志
日本総合研究所編 ダイヤモンド社
『ガイドツアー 複雑系の世界 サンタフェ研究所講義ノートから』
メラニー・ミッチェル著 高橋洋訳 紀伊國屋書店
『複雑系』 M・ミッチェル・ワールドロップ 田中光彦&遠山俊征訳 新潮社
『複雑系科学の哲学概論』 菅野礼司 本の泉社
『複雑系の哲学 21世紀の科学への哲学入門』 小林道憲 麗澤大学出版界
『別冊日経サイエンス 複雑系が開く世界』 相原一幸 編 日経サイエンス社
『複雑系による科学革命』 ジョン・キャスティー著 中村和幸訳 講談社
『複雑系、諸学の統合を求めて ─文明の未来、その扉を開く』 統合学術国際研究所 晃洋書房
→
その後、展開された新たなブックサーフィンを示すと次のようなります。
『生命論パラダイムの時代』
イリヤ・プリゴジン 浅田彰 立花隆 石垣通 西山賢一 松井孝典 田坂広志 日本総合研究所編 ダイヤモンド社
『ガイドツアー 複雑系の世界 サンタフェ研究所講義ノートから』
メラニー・ミッチェル著 高橋洋訳 紀伊國屋書店
『複雑系』 M・ミッチェル・ワールドロップ 田中光彦&遠山俊征訳 新潮社
『複雑系科学の哲学概論』 菅野礼司 本の泉社
『複雑系の哲学 21世紀の科学への哲学入門』 小林道憲 麗澤大学出版界
『別冊日経サイエンス 複雑系が開く世界』 相原一幸 編 日経サイエンス社
『複雑系による科学革命』 ジョン・キャスティー著 中村和幸訳 講談社
『複雑系、諸学の統合を求めて ─文明の未来、その扉を開く』 統合学術国際研究所 晃洋書房
…
◎ そのような、さらなるブックサーフィンを展開する中で、まさに“第3の論文『一般3Steps理論と“複雑系の科学”について』”の構想が育ち始めました。
→ このような、さらなるブックサーフィンのおかげで、第3の論文『要素還元主義の成果を包含する“複雑系の科学”の本質』が育まれるに至りました。
◎ この構想をサポートとして下さった、さらなるブックサーフィンの具体例については、研究論文『一般3Steps理論と“複雑系の科学”について』の参考文献の中に挙げております。
→※さらなるブックサーフィンの詳細については、研究論文『要素還元主義の成果を包含する“複雑系の科学”の本質』の参考文献の中に挙げております。
◎ 今から振り返れば── 『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』を、当時、3冊目の本として無理してでも購入していればよかったのかもしれません。
そうしていれば、もしかしたら、ブックサーフィンも、実際より、もっと効率的に展開できたかもしれません。
→ 今から振り返れば、『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』を、当時、3冊目の本として無理してでも購入しておけばよかったのかもしれません。
そうしていれば、もっと効率的にブックサーフィンを展開できたのかもしれません。
◎ 遠回りして、自分で文献を調べて学んだり、自分で感じたり考えたり… してきたことの蓄積があったからこそ、今、この本の多くの部分について、バンバンと響いてくる本として共感的に読めるのではないか? 現在、自分なりに読みこなせるようになっているのは、この15年間の体験のおかげなのではないか? と思うとき── “15年越し”というブランクにも、それなりに意味があったのだと感じられます。
→「遠回りして、自分で文献を調べて学んだり、自分で感じたり考えたり… の蓄積があったからこそ、この本の多くの部分に共感できる(バンバンと響かされる)ようになったのではないか?」「自分なりに読みこなせるようになったのは、それまでの15年間の体験のおかげなのではないか?」と思うとき── “15年越し”というブランクにも、それなりに意味があったのだと思います。
◎ 一方、自分で作っていた『7つの地図』を持ちながらその価値を確かめるべく、『imidas(イミダス)1992』に再会したからこそ、そこに大きな意味が生まれたのだと思います。
→ 一方、自分で育てた『7つの地図』(『7つのパラダイム』の前々身)を持ちながら、その価値を確かめるべく『imidas(イミダス)1992』に再会したからこそ、そこに大きな意味が生まれたのだと思います。
◎ やはり、この『imidas(イミダス)1992』との「8年越しの再会」も、意味のある“遠回りブックサーフィン&時間差ブックサーフィン”に相当するものだったと言えると思います。
→ やはり、この『imidas(イミダス)1992』との「8年越しの再会」も、意味のあった“遠回りブックサーフィン&時間差ブックサーフィン”に相当していると思います。
◎『imidas(イミダス)1992』は、2000年当時、インターネットができる環境を持っていなかった筆者に、“ミニ・インターネット”の役割も果たして下さったと言うこともできると思います。
→※『imidas(イミダス)1992』は、2000年当時、インターネットができる環境を持っていなかった筆者に、“ミニ・インターネット”の役割も果たしてくださったのだと思います。
◎ 将来、本当に研究するんだったなら、この本は、きっと必要だろうし、きっと役立つだろう。…
と考えて『imidas(イミダス)1992』を購入したことを思い出すならば、これも、やはり、「“あのとき感じた予感は本物♪”状態」(※『ダイアモンド』 byプリンセスプリンセス)と言えるかもしれません。
→「将来、本当に学問するなら、この本の内容も、いずれ、きっと必要となるだろうし、きっと役立つだろう。…」のように思って『imidas(イミダス)1992』を購入したことを思い出せば、これも、やはり、「“あのとき感じた予感は本物♪”状態」(※『ダイアモンド』 byプリンセスプリンセス)なのかもしれません。
◎ かつての動機付け本『imidas(イミダス)1992』は、“ひな鳥の巣立ちを促す親鳥のように、背中を押し、大きく羽ばたかせてくれた”とも言えると思います。
→ かつての「自分を見失わないための本『imidas(イミダス)1992』」は、“ひな鳥の巣立ちを促す親鳥のように、背中を押し、大きく羽ばたかせてくれた”のだと思います。
◎ (近年(2016年)、『“imidas1992”』の中に、“スピノル”についての説明が載っているのを見つけて感動しました。やはり、この本にも、ものすごさ、畏敬の念… を感じます)
→※2016年に、『imidas(イミダス)1992』の中に、“スピノル”についての説明が載っているのを見つけて感動しました。やはり、この本にも、ものすごさ、畏敬の念… を感じます。
◎ 本の本質は、古いかどうかより── やはり、(タイミングや“読者の状態(or 心の成熟度)”を含むところの)“相性”なのだと思います。
→ ときに、新しさが本の魅力になる一方で、ときに、たとえ古くても魅力がゆるがない場合もあるのだと思います。その魅力を決めるのは、結局は、(タイミングや“読者の状態(or 心の成熟度)&目的”を含むところの)相性のよさなのだと思います。
◎キーワード「“自己組織化”“I.プリゴジーヌ”“散逸構造(「非平衡開放系」)”“カオス”“三個の自由度”…」に出会いました。
→「“自己組織化”“I.プリゴジーヌ”“散逸構造(「非平衡開放系」)”“カオス”“三個の自由度”…」というキーワードに出合いました。
◎
| 『〜注目すべきことは、わずか三個の自由度をもつ力学系においてすでにカオスが可能だということである』(『imidas(イミダス)1992』 p.735 下線は、筆者による) |
→
| …注目すべきことは、わずか三個の自由度をもつ力学系においてすでにカオスが可能だということである。(『imidas(イミダス)1992』 p.735)下線は、筆者によります。 |
◎
『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』
(田坂広志、講談社)
特に『創発の三つの条件』の部分
(『“imidas1992”』のキーワード→書店→) |
あの日出会った『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』の中の“自己組織化の3つの条件”(“創発の三つの条件”の項目)に記述が── 『混沌からの秩序』を購入する背中を押して下さりました。
|
→
(『“imidas1992”』のキーワード→書店→)
『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』
(田坂広志、講談社)
|
あの日出会った『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』(特に『創発の三つの条件』の部分)が、『混沌からの秩序』や『複雑系入門』を購入する背中を押してくださりました。
|
◎
『混沌からの秩序』
(I.プリゴジン/I.スタンジェール
伏見康治・伏見譲・松枝秀明訳 みすず書房)
((『“imidas1992”』のキーワード→書店→
『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』
(『創発の三つの条件』の部分))→)
|
『“imidas1992”』にも登場していたプリゴジン。
当時、身を切る思いで、思い切って購入しました。 そのとき、背中を押したのが、やはり『複雑系の知』の中の紹介されていた「“自己組織化の3つの条件”(byプリゴジン)」に関する部分でした。この“自己組織化の3つの条件”(byプリゴジン)こそが、『7つの地図』の根拠になるはずだ!という確信を得たので、かなり無理しました。それほど“科学的な根拠”に飢えていたのだと思います。
その後、家でかじりつくように読みました。 しかし、当時、実質上は、『複雑系の知』の中で触れられていた“自己組織化の3つの条件”以上のものは、得られなかったように記憶しています。やや難解であり、この本の中に、確かに3つの条件のそれぞれについて、ある程度述べられていました。そして、そのことを確認することだけで精一杯でした。(プリゴジン自身が“3つの条件”として、まとめていたわけではありませんでした)
そして、今、この本の、抽象的な“言葉(用語)や図”を駆使しての説明が持つ難解さ(わかりにくさ)に、“複雑系の科学”が抱える問題の1つが潜んでいると考えております。
|
→
(『“imidas1992”』のキーワード→書店→
『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』
(特に『創発の三つの条件』の部分)→)
『混沌からの秩序』
(I.プリゴジン/I.スタンジェール
伏見康治・伏見譲・松枝秀明訳 みすず書房)
|
『“imidas1992”』にも登場していたプリゴジン。
当時、身を切る思いで、思い切って購入しました。そのとき、背中を押したのが、やはり『複雑系の知』の中の紹介されていた「“自己組織化の3つの条件”(byプリゴジン)」に関する部分でした。この“自己組織化の3つの条件”(byプリゴジン)こそが、『7つの地図』の根拠になるはずだ!という確信を得たので、かなり無理しました。それほど“科学的な根拠”に飢えていたのだと思います。
その後、家でかじりつくように読みました。しかし、当時、実質上は、『複雑系の知』の中で触れられていた“自己組織化の3つの条件”以上のものは、得られなかったように記憶しています。やや難解であり、この本の中に、確かに3つの条件のそれぞれについて、別々のところで、ある程度述べられていました。そして、そのことを確認することだけで精一杯でした。(プリゴジン自身が“3つの条件”として、まとめていたわけではありませんでした)
のちに、この本の、抽象的な“言葉(用語)や図”を駆使しての説明が持つ難解さ(わかりにくさ)に、“複雑系の科学”が抱える問題の1つが潜んでいると思うに至りました。
|
◎
『複雑系入門 知のフロンティアへの冒険』
(井庭崇 福原善久 NTT出版)
(『“imidas1992”』のキーワード→
『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』→)
→
『フラクタルってなんだろう』
(高安秀樹、高安美佐子著 ダイヤモンド社)
『フラクタルとはなにか』
(小川泰著 岩波書店)
『鏡の伝説』
(ブリッグス F.D.ピート 著 高安英樹、高安美佐子訳
ダイヤモンド社)
『図解雑学 複雑系』
(今野紀雄 ナツメ社)
『自己組織化とは何か』
(都甲潔 江崎秀 林健司 講談社ブルーバックス)… |
あの日出会った『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』は、一方で『複雑系入門』を購入する背中を押して下さりました。
『複雑系入門』の魅力の1つは、本書の中のリンゴの図です。“分子から、リンゴへの創発”を意味するその図のおかげで“複雑系”を身近に感じました。 “複雑系”という、見るからに難解そうな分野へのチャレンジしてみようとする意欲を生みました。
この本のすぐれている点は、大局観(概要、鳥瞰図、overview…)を与えてくれることと、ナビゲーター(水先案内人)として、ブックサーフィンでの“ハブ本”のようなものとしての役割を果たしうるところだと思います。
この本は、特に、コッホ曲線との初めての出会いを提供してくださりました。そして、自然が“フラクタル”の概念と深く関連していることを、はっきりと示してくださりました。
このことが、“3Stepsがフラクタルである”というアイデアにたどり着くヒントとなりました。
|
→
(『“imidas1992”』のキーワード→書店→
『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』
(特に『創発の三つの条件』の部分)→)
『複雑系入門 知のフロンティアへの冒険』
(井庭崇 福原善久 NTT出版)
→
『フラクタルってなんだろう』
(高安秀樹、高安美佐子著 ダイヤモンド社)
『フラクタルとはなにか』
(小川泰著 岩波書店)
『鏡の伝説』
(ブリッグス F.D.ピート 著 高安英樹、高安美佐子訳
ダイヤモンド社)
『図解雑学 複雑系』
(今野紀雄 ナツメ社)
『自己組織化とは何か』
(都甲潔 江崎秀 林健司 講談社ブルーバックス)
… |
あの日出会った『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』は、一方で『複雑系入門』を購入する背中を押してくださりました。
『複雑系入門』の魅力の1つは、本書の中のリンゴの図です。“分子から、リンゴへの創発”を意味するその図のおかげで“複雑系”を身近に感じました。“複雑系”という、見るからに難解そうな分野へのチャレンジしてみようとする意欲を生みました。
この本のすぐれている点は、大局観(概要、鳥瞰図、overview…)を与えてくれることと、ナビゲーター(水先案内人)として、ブックサーフィンでの“ハブ本”のようなものとしての役割を果たしうるところだと思います。
この本は、特に、コッホ曲線との初めての出会いを提供してくださりました。そして、自然が“フラクタル性”と深く関連していることを、はっきりと示してくださりました。
このことが、“3ステップスがフラクタルである”というアイデアにたどり着くヒントとなりました。
|
◎
『自己組織化と進化の論理』
(スチュアートカウフマン 米沢富美子監訳
日本経済新聞社)
(パラダイム・ブック
→ハイパーサイクル
→『複雑系入門』→本の中のカウフマン→)
|
『パラダイム・ブック』で出会った(2012年〜)“ハイパーサイクル”って、たぶん『複雑系入門』の中のどこかにあったような気がする、と思い『複雑系入門』を読み返してみましたが、どこにもありませんでした。よく確認すると、筆者が、ハイパーサイクルと勘違いしたのは、カウフマンネットワークのことだと分かりました。そして、そのことがきっかけで、『自己組織化と進化の論理』(スチュアートカウフマン)を読んでみることとしました。おかげで、最初の生命の誕生についての洞察が深まりました。 |
→
(パラダイム・ブック
→ハイパーサイクル
→『複雑系入門』→本の中のカウフマン→)
『自己組織化と進化の論理』
(スチュアートカウフマン 米沢富美子監訳 日本経済新聞社)
|
『パラダイム・ブック』で出合った(2012年〜)“ハイパーサイクル”って、たぶん『複雑系入門』の中のどこかにあったような気がする、と思い『複雑系入門』を読み返してみましたが、どこにもありませんでした。よく確認すると、筆者が、ハイパーサイクルと勘違いしたのは、カウフマンネットワークのことだと分かりました。それがきっかけで、『自己組織化と進化の論理』(スチュアートカウフマン)を読んでみることにしました。おかげで、最初の生命の誕生についての洞察が深まりました。 |
◎
『知恵の樹』
(ウンベルト・マトゥラーナ、
フランシスコ・バレーラ 管啓次郎訳
ちくま学芸文庫)
(パラダイム・ブック
→一般システム論、システム理論
→第三世代のシステム論(by インターネット)
→オートポイエーシス
→『複雑系入門』(by 索引)オートポイエーシス→)
|
『パラダイム・ブック』がきっかけで、ネットを通じて、第三世代のシステム論&オートポイエーシスというものを知り── 『複雑系入門』を開いてみたら、この中にもあることに気づきました。
そして、『複雑系入門』の中で紹介されていた『知恵の樹』(オートポイエーシスについての本)を読んでみることにしました。 3Steps理論と調和していると思います。 7Cを持って読み進めていくことで理解が深まるところがあると思います。 |
→
(『パラダイム・ブック』
→一般システム論、システム理論
→第三世代のシステム論(by インターネット)
→オートポイエーシス
→『複雑系入門』(by 索引)オートポイエーシス→)
『知恵の樹』
(ウンベルト・マトゥラーナ、
フランシスコ・バレーラ 管啓次郎訳 ちくま学芸文庫)
|
『パラダイム・ブック』がきっかけで、ネットを通じて第三世代のシステム論&オートポイエーシスを知り、その後『複雑系入門』の中にあることにも気づきました。
『複雑系入門』の中で紹介されていた『知恵の樹』(オートポイエーシスについての本)を読んでみました。3ステップス哲学と調和していると思います。7C(7つのパラダイムの前身)を持って読み進めることで理解が深まるところがあると思いました。 |
◎
『複雑系の経営
「複雑系の知」から経営者への七つのメッセージ』
(田坂広志)
(中古本屋さんにて)
『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』
(田坂広志)
(byネットで検索にて、15年越しに再会)
→
『未来を予見する「5つの法則」』
田坂広志 光文社
『成長するマネジャー 12の心得
なぜマネジメントが壁に突き当たるのか』
田坂広志 東洋経連
『これから市場戦略はどう変わるのか
異業種連合7つの戦略』
田坂広志 ダイヤモンド社)…
(byネットで検索)
→
『生命論パラダイムの時代』(イリヤ・プリゴジン
浅田彰 立花隆 石垣通
西山賢一 松井孝典 田坂広志
日本総合研究所編 ダイヤモンド社)
『ガイドツアー 複雑系の世界
サンタフェ研究所講義ノートから』
メラニー・ミッチェル著 高橋洋訳 紀伊國屋書店
『複雑系』 M・ミッチェル・ワールドロップ
田中光彦&遠山俊征訳 新潮社
『複雑系科学の哲学概論』 菅野礼司 本の泉社
『複雑系の哲学 21世紀の科学への哲学入門』
小林道憲 麗澤大学出版界
『別冊日経サイエンス 複雑系が開く世界』
相原一幸 編 日経サイエンス社
『複雑系による科学革命』
ジョン・キャスティー著 中村和幸訳 講談社
『複雑系、諸学の統合を求めて
─文明の未来、その扉を開く』
統合学術国際研究所 晃洋書房
『還元主義を超えて』
アーサー・ケストラー編著 池田善昭監訳 工作舎
『生命 有機体論の考察』
フォン・ベルタランフィ
長野敬・飯島衛 共訳 みすず書房
『散逸構造』
ニコリス プリゴジーヌ
小畠陽之助 相沢洋二訳 岩波書店
『複雑性の探求』 G・ニコリス/I・プリゴジン
我孫子誠也・北原和夫訳 みすず書房
『構造・安定性・ゆらぎ』 ─その熱力学的理論
グランドルフ/プリゴジン
松本元・竹山協三訳 みすず書房
…
(byネットで検索)
|
「自己組織化の3つの条件は、どこにあったっけ?」
という問題意識を持っていた中で、『複雑系の経営「複雑系の知」から経営者への七つのメッセージ』(田坂広志)と中古本屋さんにて出会い、
『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』(田坂広志)と、ネットで検索にて再会しました。
すごい本たちです!
さまざまな貴重なキーワードがたくさんあります。
経営に関心があろうがなかろうが関係なく、多いに学べたり、共感できたりすることが多々あると思います。
“複雑系が何なのか”“複雑系”“創発”“自己組織化”の意味を理解するためにも多いに役立つと思います。(本書の趣旨は「複雑系とはなにか?」ではなく、「複雑系は何に役立つか?」であると書かれておりますが──)
非常に示唆に富んでいる内容にあふれています。
これらの出会い&再会をきっかけとして、田坂広志氏の本を何冊か読ませて頂きました。
“優しい励まし”のようなものを頂いております。
心から感謝いたしております。
その後、複雑系の科学をもっとしっかり広く学ぶべきだと感じ、ネット検索によって、さまざまな本と出会いました。
その後、複雑系について、もっとしっかり学び直そうと思い、複雑系に関するさまざまな本に出会いました。 そして、これらの出会いは、『パラダイムブック』をきっかけとした出会いと合流しました。
その結果、『一般3Steps理論と“複雑系の科学”について』の論文を書く構想が育つこととなりました。
|
→
(中古本屋さんにて遭遇)
『複雑系の経営
「複雑系の知」から経営者への七つのメッセージ』
田坂広志 東洋経済
(ネットで検索にて、15年越しに再会)
『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』
田坂広志 講談社
→
(byネット検索)
『未来を予見する「5つの法則」』
田坂広志 光文社
『成長するマネジャー 12の心得
なぜマネジメントが壁に突き当たるのか』
田坂広志 東洋経連
『これから市場戦略はどう変わるのか
異業種連合7つの戦略』
田坂広志 ダイヤモンド社 …
→
(byネット検索)
『生命論パラダイムの時代』
(イリヤ・プリゴジン 浅田彰 立花隆 石垣通 西山賢一
松井孝典 田坂広志 日本総合研究所編 ダイヤモンド社)
『ガイドツアー 複雑系の世界
サンタフェ研究所講義ノートから』
メラニー・ミッチェル著 高橋洋訳 紀伊國屋書店
『複雑系』 M・ミッチェル・ワールドロップ
田中光彦&遠山俊征訳 新潮社
『複雑系科学の哲学概論』 菅野礼司 本の泉社
『複雑系の哲学 21世紀の科学への哲学入門』
小林道憲 麗澤大学出版界
『別冊日経サイエンス 複雑系が開く世界』
相原一幸 編 日経サイエンス社
『複雑系による科学革命』
ジョン・キャスティー著 中村和幸訳 講談社
『複雑系、諸学の統合を求めて
─文明の未来、その扉を開く』
統合学術国際研究所 晃洋書房
『還元主義を超えて』
アーサー・ケストラー編著 池田善昭監訳 工作舎
『生命 有機体論の考察』
フォン・ベルタランフィ 長野敬・飯島衛 共訳 みすず書房
『散逸構造』
ニコリス プリゴジーヌ 小畠陽之助 相沢洋二訳 岩波書店
『複雑性の探求』 G・ニコリス/I・プリゴジン
我孫子誠也・北原和夫訳 みすず書房
『構造・安定性・ゆらぎ ─その熱力学的理論』
グランドルフ/プリゴジン 松本元・竹山協三訳 みすず書房
… |
「自己組織化の3つの条件は、どこにあったっけ?」という問題意識の中で、中古本屋さんにて『複雑系の経営「複雑系の知」から経営者への七つのメッセージ』(田坂広志 東洋経済)と出会い、その後のネット検索にて『複雑系の知 二十一世紀に求められる七つの知』(田坂広志 講談社)と再会しました。
すごい本たちです! 非常に示唆に富む内容にあふれています。さまざまな貴重なキーワードがたくさんあります。経営に関心があろうがなかろうが関係なく、学べたり共感できたりすることが多々あると思います。
本書の趣旨は「複雑系とはなにか?」ではなく、「複雑系は何に役立つか?」であると書かれていますが、「複雑系が何なのか? 複雑系、創発、自己組織化の意味」を学ぶためにも役立つと思いました。
これらの出会い&再会をきっかけとして、田坂広志氏の本を何冊か読ませて頂きました。“優しい励まし”のようなものを頂きました。心から感謝いたしております。
その後、複雑系の科学をもっとしっかり広く学ぶべきだと感じ、ネット検索によって、複雑系に関するさまざまな本と出会いました。これらの出会いは、『パラダイムブック』をきっかけとした出会いと合流しました。その結果、『一般3Steps理論と“複雑系の科学”について』(『要素還元主義の成果を包含する“複雑系の科学”の本質』の前身)の論文の構想が育ちました。
|
◎ こういった複雑系に関するブックサーフィン(2015年4月〜)を通じて、第3の論文『一般3Steps理論と“複雑系の科学”について』の構想が育ち始める一方で── 『“imidas1992”』の中の「3つの自由度でカオス」というキーワードに再会したのみならず、「決定論的カオス」というキーワードに出会った筆者は、“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)をさらにグレードアップさせるためのヒントを得ることとなりました。
そうして、物理学についてのさらなるブックサーフィンも、再び展開されることとなり、その結果、2016年12月1日、『“現代物理学”が陥った行き詰まり、困難、迷走… を解消する新しい手段の紹介』(一般3Steps理論&“EMOES”(素スピノールからの創発モデル)ver.2.00)』をアップできるまでにこぎ着けました。
(→『旅人』)
そして、一方で、ずっとあたため続けていた、第3の論文『一般3Steps理論と“複雑系の科学”について』も、2016年12月27日、ようやく、アップにこぎ着けるに至りました。
こういった研究を進められるのは、研究論文『一般3Steps理論と“複雑系の科学”について』の参考文献の中に挙げた、すべての著者の方々、出版社の方々、書店の方々… のおかげであるのは、もちろんです。
→
こういった複雑系に関するブックサーフィン(2015年4月〜)のおかげで、第3の論文『一般3Steps理論と“複雑系の科学”について』(『要素還元主義の成果を包含する“複雑系の科学”の本質』の前身)の構想が育ちました。
※一方で、 『imidas(イミダス)1992』の中の「3つの自由度でカオス」というキーワードとの再会や、他書での「決定論的カオス」というキーワードとの出合いによって、物理学の研究をさらにグレードアップさせるためのヒントを与えてくださりました。
これらの成果が得られたのは、上に挙げた本、さらには研究論文『要素還元主義の成果を包含する“複雑系の科学”の本質』の参考文献に挙げた本の、すべての著者の方々、出版社の方々、書店の方々… のおかげです。
心から感謝いたしております。
『進化の傷あと』
◎ 背表紙のタイトル『進化の傷あと』の中の“進化”の部分に魅かれて、この本を手に取ってみた。
→ 背表紙のタイトル『進化の傷あと』の中の“進化”の部分に惹かれて、この本を手に取ってみた。
◎
そして、少なくとも進化についての何らかのヒントは与えてくれるだろう、と言う軽い期待を抱いて、お試し的に購入を決意した。
→
そして、「少なくとも進化についての何らかのヒントを与えてくれるだろう」という軽い期待を抱いて、お試し的に購入を決めた。
◎ 大した期待をせずに購入した、この『進化の傷あと──身体が語る人類の起源──』を、後にじっくりと読んでみた筆者 は、大きな衝撃を受けました。
目からウロコがパラリパラリと落ちまくりました。
→ 大した期待をせずに購入した、この『進化の傷あと』を、のちにじっくりと読んでみた筆者 は、衝撃を受けました。目からウロコをパラリパラリと落としまくりました。
◎追加 ※この書名の中の“人類”は、自然人類学の人類を意味しています。のちの説明と混乱を避けるために、以下では、“人類”の代わりに“ヒト”を使うことにします(なお、ヒトという言葉は、イヌ、ネコ、チーター、ライオン、ゾウ、イルカ… と同じ系列の言葉です)。
◎ なぜ、汗と一緒に、貴重な塩分も外に出してしまうのか?
なぜ、体内の塩分不足を本能的に察知し、塩を求めて大移動する動物がいる中で、人類は、その本能を失い熱中症にかかるリスクを引き受けたのか?
なぜ、人は,皮下脂肪が多くたまりやすいのか?
なぜ,人は、自分の意思通りに自由自在に呼吸をコントロールできるのか?
なぜ,霊長類で人だけが言葉をしゃべれるのか?
なぜ、人は、泳ぐのか?(なぜ、人は、水泳ができるのか?)
なぜ、人間の赤ちゃんは、生まれてすぐに泳げるのか?
なぜ、海女さんは、長く海で働けるのか?
なぜ、霊長類で人だけに軟口蓋があるのか?
なぜ、人は、体毛が少ないのか?
なぜ、“貝塚”が発掘されているのか?
なぜ、“魚を食べると頭がよくなる♪”という歌が存在するのか?
なぜ、人類の大昔の化石の多くは、“過去の水辺(特に海岸)”で発見されているのか?
なぜ、人は、キャンプをするとき、ふつう、海辺、湖畔、川辺などの水辺を選ぶのか?
なぜ、古代四大文明が、川辺(黄河、インダス川、ユーフラテス川、ナイル川…)で発生したのか?
なぜ、現代人は、水道を作って生活しているのか?
…
→ なぜ、ヒトは汗と一緒に貴重な塩分も外に出してしまうのか?
なぜ、体内の塩分不足を本能的に察知し、塩を求めて大移動する動物がいるのに、ヒトは、その本能を失い熱中症にかかるリスクを引き受けたのか?
なぜ、ヒトは皮下脂肪が多くたまりやすいのか?
なぜ、ヒトは自分の思いのままに自由自在に呼吸をコントロールできるのか?
なぜ、霊長類でヒトだけが言葉をしゃべれるのか?
なぜ、ヒトは水泳をするのか?
なぜ、ヒトの赤ちゃんは、生まれてすぐに泳げるのか?
なぜ、海女さんは長く海で働けるのか?
なぜ、霊長類でヒトだけに軟口蓋があるのか?
なぜ、ヒトは体毛が少ないのか?
なぜ、“貝塚”が発掘されているのか?
なぜ、“魚を食べると頭がよくなる♪”という歌が存在するのか?
なぜ、ヒトの大昔の化石の多くは、“過去の水辺(特に海岸)”で発見されているのか?
なぜ、キャンプをするとき、ヒトは、海辺、湖畔、川辺などの水辺をふつう選ぶのか?
なぜ、古代四大文明が川辺(黄河、インダス川、ユーフラテス川、ナイル川…)で発生したのか?
なぜ、ヒトは水道を作って生活しているのか?
…
◎ サバンナ説だけでは説明しにくいこれらのことを、ただ1つの仮説(“水辺(特に海辺)で生活していた時期が人類を誕生させた”)を取り入れるだけで、スパッスパッとすっきりと説明できることを、この『進化の傷あと──身体が語る人類の起源──』が、気づかせて下さりました。
→ サバンナ説だけでは説明しにくいこれらのことを、ただ1つの仮説(“水辺(特に海辺)で生活していた時期がヒトを誕生させた”)を取り入れるだけで、スパッスパッとすっきりと説明できることを、この『進化の傷あと』が気づかせてくださりました。
◎ 非常に見事です。
→見事です。
◎
この 『進化の傷あと──身体が語る人類の起源──』に出会うまでは、筆者は 、常識的に 、“アフリカのサバンナ で、二足歩行を開始したことがきっかけで、人類が誕生した”と思っておりました。
しかし、 この『サバンナ生活が人類を生んだ説』の常識が、必ずしも絶対的なものではないことに、この 『進化の傷あと──身体が語る人類の起源──』のおかげで気づくことができました。
→ この 『進化の傷あと』に出会うまでは、筆者は常識的に“アフリカのサバンナ 生活(by 二足歩行)が理由でヒトが誕生した”と思っておりました。
しかし、 この『サバンナ生活(byに二足歩行)がヒトを生んだ説』の常識が、必ずしも絶対的なものではないことに、この 『進化の傷あと』のおかげで気づくことができました。
◎ そして、直観的にも、さまざまな知識(生理学、解剖学…) と重ねても、 『進化の傷あと──身体が語る人類の起源──』の説明の方が、 どうも自然&合理的であり、単純明瞭で、納得しやすいように思われました。
→ 直観的にも、さまざまな知識(生理学、解剖学…) を重ねても、 『進化の傷あと』の説明の方が、 どうも無理なく合理的であり、単純明解で納得しやすいように思われました。
◎ 当然、“水辺(特に海辺)生活が 人類を生んだ説” は、“後件肯定”による“大胆な推理”に過ぎません。 (参考…『論理的に考えること』)
しかし、「“後件肯定”による“大胆な推理”」に過ぎないことは、“サバンナ生活が人類を生んだ説”も同様のことです。
→ 当然、“水辺(特に海辺)生活が ヒトを生んだ説” は、“後件肯定”による“大胆な推理”に過ぎません(参考 『論理的に考えること』(マイ・ブックサーフィン『3年 全国大学 国語入試問題詳解』))。
しかし、「“後件肯定”による“大胆な推理”」に過ぎないことは、“サバンナ生活がヒトを生んだ説”も同様です。
◎ そして、その「“後件肯定”による“大胆な推理”であること」という条件は全く同じであるのに関わらず ── そして、“水辺(特に海辺)生活が 人類を生んだ説” の方が、“サバンナ生活が人類を生んだ説”よりも、はるかに見事に広い範囲のことを説明できているのに関わらず──
科学会では、相変わらず、“水辺(特に海辺)生活が人類を生んだ説” を“異端の説”として扱 い続けていることを知りました。
すなわち、 後々、出会った他の本等によって── “(自然人類学の)専門家”の方々の間では、この“水辺(特に海辺)生活が 人類を生んだ説” が、「ゼッタイありえない」ものとして、「否定、拒否、拒絶、非難…」or「軽視、無視、スルー…」され続けていることも知りました。
→ のちに、「後件肯定による大胆な推理」という条件は全く同じであるのに関わらず 、なおかつ、“水辺(特に海辺)生活が ヒトを生んだ説” の方が“サバンナ生活がヒトを生んだ説”よりも、はるかに見事に広い範囲のことを説明できているのに関わらず── 相変わらず、“水辺(特に海辺)生活がヒトを生んだ説” が“異端の説”として扱 われ続けていることを知りました。
すなわち、 後々出会った他の本等によって、“(自然人類学の)専門家”の方々は、“水辺(特に海辺)生活が ヒトを生んだ説” が「ゼッタイありえない」として「否定、拒否、拒絶、非難…」or「軽視、無視、スルー…」し続けていることを知りました。
◎ なぜなのでしょうか?
やはり、ここにあるのは、 典型的な“「協調(調和)をめざさない闘争」路線であると思います。
→ やはり、ここにあるのは、 典型的な“『Against』『Out』”『For』『In』路線であると思います。
◎ ここにあるものは、もはや、本来の研究の営み、すなわち、「自然(nature)との調和を探究する営み」ではなくなってしまっている恐れがあると思われます。
→ ここにあるのは、もはや、学問の本来の営み、すなわち、「自然(nature)との調和を探究する営み」ではなくなってしまっていると思われます。
なぜなのでしょうか?
◎ やはり、『(知識の専門家であると同時にその知識によって生計を立てている)職業科学者(プロの科学者)』 である方々にとって、「定説(伝統、権威…)を覆しかねない説を支持することによって ── 学会内で、村八分にあってしまったり、ポストを失ってしまったりする」という危機感は、相当なものなのだろうと思われます。
しかし、定説(伝統、権威…)を覆しかねない説であるという理由だけで、 「否定、拒否、拒絶、非難…」or「軽視、無視、スルー…」され続けることは、不毛だと思います。
あくまで大事なことは、定説(伝統、権威…)を覆しかねない説であるかどうかではなく、やはり、自然(nature)と調和しているかどうかであるはずです。
少なくとも、“水辺(特に海辺)生活が人類を生んだ説”についても、自然(nature)と調和しているところがあれば、その部分を尊重することが、『職業科学者(プロの科学者)』である方々 に、求められているのではないでしょうか?
→ やはり、『(知識の専門家であると同時にその知識によって生計を立てている)職業科学者(プロの科学者)』 の方々にとって、定説(伝統、権威…)を覆しかねない説を支持することによって 、学会内で村八分にあってしまったり、ポストを失って 食えなくなってしまったりする危機感が大きいからなのだろうと思われます。
その『(知識の専門家であると同時にその知識によって生計を立てている)職業科学者(プロの科学者)』に、定説(伝統、権威…)を覆しかねない説であるかどうかではなく、やはり、自然(nature)と調和しているかどうかが大事だと訴えることは酷なことなのつ。
◎ 後に、日系サイエンス(2010年5月号)にて、“なぜ、毛がないのか?”という特集記事を読ませて頂きました。
→のちに読んだ日系サイエンス(2010年5月号)の“なぜ、毛がないのか?”という特集記事は、定説(伝統、権威…)を覆しかねない説を支持することによって、学会内で村八分にあってしまったり、ポストを失って食えなくなってしまったりする危機感から、やむを得ず紡がれたものに過ぎないのかもしれません。
◎削除
それを読むと、やはり、“サバンナ生活が人類を生んだ説”を支持する根拠(“水辺(特に海辺)生活が人類を生んだ説”を否定する根拠)が、きわめて脆弱なものであることがわかります。
(1)例えば、水中は、「ワニがいて危険だから“水辺生活が人類を生んだ説”はありえない」という説明があります。 この説明は、“サバンナ生活が人類を生んだ説”自体の首もしめています。 なぜなら、サバンナも、ライオンやチーターがいて、十分に危険だからです。
(なお、ライオンやチーターがいないサバンナが実在するように、ワニのいない水辺(特に海辺)も実在します)
そもそも、なぜ、わざわざ好き好んで、よりによって水の少ないサバンナを選んで暮らし続ける必要があったのでしょうか? われわれの中には、安全な水辺を探して、その水辺に移動していこうとする(安全な水辺とコンタクトを取り続けようとする)本能が残っているのではないでしょうか?
(2)例えば、「ラッコやトドなどの水辺の動物でも無毛化していない例があるから問題だ」という説明があります。 この説明は、“サバンナ生活が人類を生んだ説”自体の首も閉めており、説得力がありません。
もし「無毛化&汗によって身体を冷やすことが大事だった」というサバンナ説の主張が正しいとしたなら、サバンナに暮らすヒヒが無毛化していないのは、なぜなのでしょうか?
チーターやライオン、インパラが無毛化していないのは、なぜなのでしょうか?
移動能力があれば、涼しい場所に移動すればよいだけではないでしょうか?
(3)“水辺生活が人類を生んだ説”が『複雑すぎる』という主張は、やはり、“サバンナ生活が人類を生んだ説”自体の首をも閉めています。
例えば、『頭髪に関しては、直射日光による異常な高温から頭部を守るために保持されたのだろう。この説明は矛盾しているように聞こえるかもしれないが』という記述がありますが、明らかに矛盾しています。
なぜなら、全身も同じように、頭部と同様なしくみで高温から守った方がより“単純”なはずだからです。
そもそも、単純か複雑かは、相対的なものに過ぎません。 自然(nature)と調和しているかどうかこそが、大事なのだと思います。
…
|
つまり、“サバンナ生活が人類を生んだ説”を支持し、“水辺(特に海辺)生活が人類を生んだ説”を否定しようとする説明は、どれもこれも「まず結果ありきの、その場しのぎの論理(“周転円たち”)」に過ぎないと判断されてもしかたがないものだと思われます。
ここで繰り広げられているものは、もはや、真の研究、すなわち、「自然(nature)との調和を探究する営み」からほど遠く── 何か違ったものになってしまっていると言われてもしかたないように思われます。
すなわち、「特定の教義を守り抜こうとして、保身的(独善的、排他的…)になり、脆弱な理論を重ねているだけの営み」になってしまっていると見なされてもしかたないと思われます。
◎ ここで繰り広げられているものは、もはや、真の研究、すなわち、「自然(nature)との調和を探究する営み」からほど遠く── 何か違ったものになってしまっていると言われてもしかたないように思われます。
すなわち、「特定の教義を守り抜こうとして、保身的(独善的、排他的…)になり、脆弱な理論を重ねているだけの営み」になってしまっていると見なされてもしかたないと思われます。
健全な研究の営みは、“徹底的に疑い、間違いに気づき、改善すること”をくり返しながら自然(nature)との調和をより高めていく営みであるはずです。
「間違いに気づくこと、間違いを発見できること、間違いを認めること…」自体は、決して恥ずかしいこと、身を滅ぼすものなどではなく、むしろ、それこそが自然(nature)との調和を高めてきた原動力であり、高く評価されるべきものであったはずです。
つまり、「“徹底的に疑い、間違いに気づき、改善すること”をくり返すこと」こそが、より自然(nature)と調和している、より深い理論を構築するために、役立ってきたはずです。
→
※ここにある問題は、「定説(伝統、権威…)を覆すことが身を滅ぼすことつながる」という社会システムなのだと思います。
どうすれば、「(定説(伝統、権威…)を覆すかどうかではなく)自然(nature)との調和性を高めることこそが評価され、身の安泰につながる」という社会システムができるのでしょうか? 詳細な検討は、今後の課題です。
◎ 当然、筆者も、人類が、“クジラやイルカやジュゴン”、すなわち、“人魚”のように、24時間“水中(特に海中)”で暮らしていた時代があったとは思っておりません。
あくまで、せいぜい、“ときに水中(特に海中)で過ごし、ときに陸上で過ごす──”そのような“水辺(特に海辺)生活”だったのだろうと思います。(水生動物と言われる“カバやワニ”も、ときには陸に上がる、“水辺生活”をしています)
→
当然、筆者も、ヒトが“クジラやイルカやジュゴン”、すなわち、“人魚”のように、24時間“水中(特に海中)”で暮らしていた時代があったとは思っておりません。あくまで、せいぜい“ときに水中(特に海中)で過ごし、ときに陸上で過ごすような水辺(特に海辺)生活”をしていたのだろうと思います。
※水生動物と言われる“カバやワニ”も“ときには陸に上がる水辺生活”をしています。
◎ つまり、「“水辺(特に海辺)”で暮らしていた時代の中で、“水中(特に海中)”の比率がある程度高まった時期に、“収斂”という現象を基礎として、人類への進化が促された」と考えるのが自然だと思います。
→ つまり、「“水辺(特に海辺)”で暮らしていた時代の中で、“水中(特に海中)”の比率がある程度高まった時期に、“収斂”という現象を基礎として、ヒトへの進化が促された」という説明が無理なく合理的なのだと思います。
◎無理なく合理的なものだと思われます→無理なく合理的だと思われます
◎“水辺(特に海辺)生活が人類を生んだ説”の方が、無理なく合理的であると判断できるのは── やはり、“現代において、もし水道や電気が全くない世界になったとしたら、現代人は、どこに住もうとするか?”を想像してみても明らかかもしれません。
→“水辺(特に海辺)生活がヒトを生んだ説”の方が無理なく合理的であると判断できるのは、やはり、“現代において、もし水道や電気が全くない世界になったら、現代人は、どこに住もうとするか?”を想像してみても明らかかもしれません。
◎なお、あらゆる植物(草木、野菜や果実、植物ブランクトン、藻類…)は、水を利用した光合成にもとづいて生育しますので、水(海水、淡水…)が豊富であるということは、植物や、その植物を食料とする動物(多様な陸上動物のみならず、魚介類を含む)が、より豊富に存在するということに他なりません)
→※なお、あらゆる植物(草木、野菜や果実、植物ブランクトン、藻類…)は、水を利用した光合成にもとづいて生育しますので、水(海水、淡水…)が豊富であるということは、植物や、その植物を食料とする動物(多様な陸上動物のみならず、魚介類を含む)が、より豊富に存在するということに他なりません。
◎ 人間にとって、水辺と言うのは、とても重要な意味があることは、疑いの余地がないことだと思います。
→ ヒトにとって水辺には非常に重要な意味があることは、疑いの余地がないと思います。
◎※なお、次のよう記述も、「水辺(特に海辺)で誕生したヒト」を支持していると思います。
→※なお、次のような記述も、「水辺(特に海辺)で誕生したヒト」を支持していると思います。
◎削除 このことは、まさに、「サバンナで誕生したヒト」よりも、「水辺(特に海辺)で誕生したヒト」の方が自然(nature)と調和していることの、決定的な証拠の一つだと言っても過言ではないかもしれません。 (詳細な検討は、今後の課題です)
◎ しかし、“サバンナ”より、“水辺(特に海辺)”の方が人類の起源としてふさわしいだろう(より自然(nature)と調和しているだろう)という提案のもっともさは、全くゆらがないと思います。
→ しかし、“サバンナ”より、“水辺(特に海辺)”の方がヒトの起源としてふさわしいだろう(より自然(nature)と調和しているだろう)という提案のもっともさは、全くゆらがないと思います。
◎ 従来の専門家の方々が、新参者(部外者、アマチュア…)であることを理由にして、やみくもに『“水辺(特に海辺)説”』を拒否、拒絶…(or 軽視、無視…)しながら、「協調(調和)をめざさない闘争」路線を取り続けているとしたら、これほど、不毛で悲しいことはないだろうと思います。
やはり、従来の専門家によるものか新参者(部外者、アマチュア…)によるものかが、研究の価値を決めるべきではなく── あくまで、「自然(nature)と調和しているかどうか」こそが、研究の価値を決めるべきだと思います。
→ やはり、「従来の専門家によるものか or 新参者(部外者、アマチュア…)によるものか」が学問の価値を決めるべきではなく、あくまで「自然(nature)と調和しているかどうか」こそが、学問の価値を決めるべきだと思います。
◎ やはり、少なくとも、“水辺(特に海辺)生活が人類を生んだ説”は、“サバンナ生活が人類を生んだ説”と対等に議論され、十分に、吟味、改善、検証… されていくべきであると思います。
→ やはり、少なくとも、“水辺(特に海辺)生活がヒトを生んだ説”は、“サバンナ生活がヒトを生んだ説”と対等に議論され、十分に、吟味、改善、検証… されるべきであると思います。
◎ それが健全な研究、すなわち、健全な「自然(nature)との調和を探究する営み」なのだと思います。
→ それが健全な学問、すなわち、「自然(nature)との調和を探究する営み」としての学問なのだと思います。
◎ そして、『進化の傷あと』を通じて学んだ、従来の科学会が持ちうる“「協調(調和)をめざさない闘争」路線を取る傾向”と「アクア説の不遇」に関して獲得した知識や知恵は、素スピノル物理学を育むために、なんらかの形で役立ってきていたのでした。
→ さらには、この『進化の傷あと』のページの執筆をきっかけにした『科学革命の構造』(クーン みすず書房)との再会、および、そこからの新たなブックサーフィンは、素スピノル物理学を客観的に見つめなおさせてくださりました。
これらのことが、素スピノル物理学を育むために役立っていたのでした。
◎ 一方で、この『進化の傷あと』は、“進化”“人類学”“人類、ヒト、人間…”、そして、よりいっそう、深く広く学び始めようとする意欲を与えて下さり、そこから新たなブックサーフィンが展開されることになりました。
このブックサーフィンのおかげで、“7つのコンパス”や“3ステップス理論”(3ステップス進化論)を、さらに進化させることができたのでした。
そして、さらに、この『進化の傷あと』のページの執筆をきっかけにした、『科学革命の構造』(クーン)との再会、およびそこからの新たなブックサーフィンは、素スピノル物理学を客観的に見つめなおさせてくださったのでした。
→ 一方で、この『進化の傷あと』は、「進化」「人類学」「人類、ヒト、人間…」を含むテーマについて、よりいっそう、深く広く学び始めようとする意欲を与えてくださり、そこから新たなブックサーフィンが展開されたのでした。
このブックサーフィンのおかげで、“3ステップス哲学”(特に3ステップス進化論)を、さらに進化させることができたのでした。
◎ 心から感謝申し上げます。
以下に、マイ・ブックサーフィンの例をまとめてみました。シナジェティック・リーディングの候補とも言えると思います。
→ 心から感謝申し上げます。
◎
『ワンダフル・ワールド』
スティーブン・ジェイ・グールド 早川書房 |
大進化、小進化…
|
『自己組織化と進化の論理』
スチュアート・カウフマン 日本経済新聞社 |
自己組織化も自然淘汰もともに大切──。 |
『「進化論」を書き換える』
池田清彦 新潮社 |
確かに進化論も進化していると思います。
|
| 『38億年 生物進化の旅』 池田清彦 新潮社 |
|
『地球生命35億年物語─進化の秘密は氷河期にあった』
ジョン・グリビン 木原悦子訳 徳間書店 |
|
『ヒトはいかにして人となったか』
テレンス・W・ディーコン 金子隆芳訳 新曜社 |
“言語と脳の共進化”
この本で“共進化”という考えを初めて知りました。 |
| →霊長類学本 |
|
『NHKスペシャル 地球大進化
46億年・人類への旅 大陸大分裂5』
NHK[地球大進化]プロジェクト[編] NHK出版 |
果物を見つけるために、立体視の力を獲得する形で
“真猿類”に進化したそうです。 |
『人類の足跡10万年全史』
スティーヴン・オッペンハイマー 仲村明子訳 草思社 |
“共進化”についても書かれています。 |
『宇宙創成から人類誕生までの自然史
140億年の9つの進化を探る』
和田純夫 ベレ出版 |
|
『目の誕生 カンブリア紀の謎を解く』
アンドリュー・パーカー 草思社 |
|
『共生生命体の30億年』
リン・マーギュリス 草思社 |
|
『死はなぜ進化したか』
ウィリアム・R・クラーク 三田出版会 |
|
『生命と地球の共進化』
川上紳一 NHKブックス
|
|
『ヒトはイヌのおかげで、人になった』
ジェフリー・M・マッソン 桃井緑美子 |
“共進化”のキーワードで検索する中で、この本の存在を初めて知りました。
|
『人は海辺で進化した 人類進化の新理論』
エイレン・モーガン 望月弘子訳 どうぶつ社
|
『進化の傷あと』の前に書かれた著書です。 |
『次の大量絶滅を人類はどう超えるか』
アナリー・ニューイッツ 熊井ひろ美訳 インターシフト |
|
『科学革命の構造』
トーマス・クーン みすず書房 |
まさに、このページをまとめている中で、『科学革命の構造』(クーン)を、しっかり読みなおそうと動機づけられました。
確かに“とてつもなく励まされる”という体験をさせて頂きました。しかし、最後まで読み進めていくと── 鵜呑みにできない部分もあることに気づきました。それが『考察7 パラダイムと「科学の進歩」について』(さんぽフルーツ研究、“現代物理学”の危機を解消する新しい手段の紹介)を生み出すきっかけの1つとなりました。
|
『パラダイムとは何か』
(野家啓一 講談社学術文庫) |
『科学革命の構造』(クーン)を、ネットで購入しようとする際に初めて出会い── その後、『科学革命の構造』を読む中で、もっと詳しく学ぶべきだと思い、購入を決めました。
やはり、確かに“とてつもなく励まされる”という体験をさせて頂きました。しかし、読み進めていくと、鵜呑みにできない部分があることに気づき、それが『考察7 パラダイムと「科学の進歩」について』を生み出すきっかけの1つとなりました。 貴重なヒントを与えて下さりました。心から感謝しております。 |
『科学の解釈学』
(野家啓一 講談社学術文庫) |
『パラダイムとは何か』がきっかけで出会い、読むべきだと思い、購入するに至りました。
大いに励まされたのみならず、目からウロコが落ちるような体験もさせて頂きました。
しかし、読み進めていくと、鵜呑みにできない部分があることに気づき── それらが、やはり『考察7 パラダイムと「科学の進歩」について』を育む、貴重なヒントとなりました。 心から感謝しております。 |
|
…
|
|
→
『ワンダフル・ワールド』
スティーブン・ジェイ・グールド 早川書房 |
大進化、小進化…
|
『自己組織化と進化の論理』
スチュアート・カウフマン 日本経済新聞社 |
自己組織化もNatural Selection〈自然淘汰&自然選択〉もともに大切──。 |
『「進化論」を書き換える』
池田清彦 新潮社 |
確かに進化論も進化していると思います。
|
| 『38億年 生物進化の旅』 池田清彦 新潮社 |
|
『地球生命35億年物語─進化の秘密は氷河期にあった』
ジョン・グリビン 木原悦子訳 徳間書店 |
|
『ヒトはいかにして人となったか』
テレンス・W・ディーコン 金子隆芳訳 新曜社 |
“言語と脳の共進化”
この本で“共進化”という考えを初めて知りました。 |
| →霊長類学本 |
|
『NHKスペシャル 地球大進化
46億年・人類への旅 大陸大分裂5』
NHK[地球大進化]プロジェクト[編] NHK出版 |
果物を見つけるために、立体視の力を獲得する形で
“真猿類”に進化したそうです。 |
『人類の足跡10万年全史』
スティーヴン・オッペンハイマー 仲村明子訳 草思社 |
“共進化”についても書かれています。 |
『宇宙創成から人類誕生までの自然史
140億年の9つの進化を探る』
和田純夫 ベレ出版 |
|
『目の誕生 カンブリア紀の謎を解く』
アンドリュー・パーカー 草思社 |
|
『共生生命体の30億年』
リン・マーギュリス 草思社 |
|
『死はなぜ進化したか』
ウィリアム・R・クラーク 三田出版会 |
|
『生命と地球の共進化』
川上紳一 NHKブックス
|
|
『ヒトはイヌのおかげで、人になった』
ジェフリー・M・マッソン 桃井緑美子 |
“共進化”のキーワードで検索する中で、この本の存在を初めて知りました。
|
『人は海辺で進化した 人類進化の新理論』
エイレン・モーガン 望月弘子訳 どうぶつ社
|
『進化の傷あと』の前に書かれた著書です。 |
『次の大量絶滅を人類はどう超えるか』
アナリー・ニューイッツ 熊井ひろ美訳 インターシフト |
|
『科学革命の構造』
トーマス・クーン みすず書房 |
まさに、このページをまとめている中で、『科学革命の構造』(クーン)を、しっかり読みなおそうと動機づけられました。
確かに“とてつもなく励まされる”という体験をさせて頂きました。しかし、最後まで読み進めていくと、鵜呑みにできない部分もあることに気づきました。
|
『パラダイムとは何か』
野家啓一 講談社学術文庫 |
『科学革命の構造』(クーン)を、ネットで購入しようとする際に初めて出会い、その後、『科学革命の構造』を読む中で、もっと詳しく学ぶべきだと思い、購入を決めました。
やはり、確かに“とてつもなく励まされる”という体験をさせて頂きました。しかし、読み進めていくと、鵜呑みにできない部分があることに気づきました。貴重なヒントを与えてくださりました。 |
『科学の解釈学』
野家啓一 講談社学術文庫 |
『パラダイムとは何か』がきっかけで出会いました。大いに励まされたのみならず、目からウロコが落ちるような体験もさせて頂きました。しかし、読み進めていくと、鵜呑みにできない部分があることに気づきました。 |
|
…
|
|
◎ その後、たまたま、中古本屋さんで、『科学的思考とは何か』(竹内均 PHP文庫)に出会いました。
→ その後、たまたま、中古本屋さんで、『科学的思考とは何か』(竹内均 PHP文庫)に出会いました。
◎ ※この本との出会いは、竹内均氏との久々の再会でもありました。竹内均氏は、ご存知の通り、科学雑誌『ニュートン』の元編集長であられたお方です。
→※この本との出会いは、竹内均氏との久々の再会でもありました。竹内均氏は、ご存知の通り、科学雑誌『ニュートン』の元編集長でした。
◎ 受験生時代に読んだ『わが息子よ、君はどう生きるか』(知的生き方文庫 三笠書房)や『自助論』(知的生き方文庫 三笠書房)が、竹内均氏による翻訳書であったので身近に感じていたのみならず── 竹内均氏自身の著作『人生を最高に生きる法』(知的生き方文庫 三笠書房)も受験生時代に読んでいたので、ファンでした。
→ 受験生時代に読んだ『わが息子よ、君はどう生きるか』(知的生き方文庫 三笠書房)や『自助論』(知的生き方文庫 三笠書房)が、竹内均氏による翻訳書であったので身近に感じていたのみならず── 竹内均氏自身の著作『人生を最高に生きる法』(知的生き方文庫 三笠書房)も受験生時代に読んでいましたので、ファンでした。
◎ この『科学的思考とは何か』(竹内均 PHP文庫)の中で最もインパクトを与えられたのは、
『(大陸移動説を唱えた)ウェゲナー』について初めて知ることのできた次の点でした。
→ この『科学的思考とは何か』(竹内均 PHP文庫)の中で最もインパクトを受けたのは、『(大陸移動説を唱えた)ウェゲナー』について初めて知ることのできた次の点でした。
◎ ※この『ウェゲナー氏』と『エイレン・モーガン氏』には、似ているところがあるように感じられたからこそ、このページに書き加えることにいたしました。
→※この『ウェゲナー氏』と『エイレン・モーガン氏』が似ているところがあると感じられたからこそ、このページに書き加えることにいたしました。
◎ 2つ目の引用文がきっかけで、『新科学哲学』(板倉聖宣 仮説社)にも出会いました。
→ 2つ目の引用の部分がきっかけで、『新科学哲学』(板倉聖宣 仮説社)にも出会いました。
◎ ※このリードしている方は、『Head』の方向の存在の例なのだと思います。
→
※このリードしている方は、学問分野における『Head』の方向の存在なのだと思います。
このリーダーは、新しい哲学の土台を提供しながら、その上に新しい分野を築いているのだと思います。 |
◎ ※この記述によると、「筆者が、例えば物理学において考えを進められるのは、3ステップス原理(3Steps Principles)があるからこそだ」ということになると思われます。
→ ※この記述によると、「筆者が、例えば物理学において考えを進められるのは、3ステップス原理(3Steps Principles)があるからこそだ」ということになります。
◎ このアブダクションは、「起源の探究」に向かう傾向があるのだそうです。
(まさに、ダーウィンの著書が『種の起原』であり、ウェゲナーの著書が『大陸と海洋の起源』であることが、これらが「アブダクション」の典型であることと調和しています)
→ このアブダクションは、「起源の探究」に向かう傾向があるのだそうです(まさに、ダーウィンの著書が『種の起原』であり、ウェゲナーの著書が『大陸と海洋の起源』であることが、これらが「アブダクション」の典型であることと調和しています)。
◎
※この構図は、『時空と物質とライフの起源─自然科学の3ステップス的原理─』の付録『科学について』の中で示した、おおよそ次の枠と調和していると思います。
|
「アリストテレスまでの時代の
自然哲学(natural philosophy)」
|
「ニュートンやアインシュタインの
時代を含む従来の自然科学(science)」
|
現代的な自然哲学
(=現代的な自然科学)
(=自然(nature)と調和
している自然哲学)
|
また、『時空と物質とライフの起源─自然科学のための3ステップス的原理─』は、まさに「起源の探究」をしていますので、第三世代に属していると思われます。
→※『時空と物質とライフの起源─自然科学のための3ステップス的原理─』は、まさに「起源の探究」をしていましたので、第三世代に属していると思われます。
◎
『科学的思考とは何か』
(竹内均 PHP文庫) |
『大陸は動いている』
(竹内均 『大地 国語 五下』 光村図書) |
『ウェゲナーの大陸移動説は仮説実験の勝利』
(西村敏雄 文芸社) |
『大陸と海洋の起源』
(アルフレッド・ウェゲナー 竹内均訳 講談社) |
『新科学哲学』
(板倉聖宣 仮説社) |
『第三世代の学問 「地球学」の提唱』
(竹内均、上山春平 中公新書) |
『アブダクション 仮説と発見の論理』
(米森裕治 勁草書房) |
『科学・モデル・アナロジー』
(M.ヘッセ/高田紀代志訳 培風館) |
→
『科学的思考とは何か』
(竹内均 PHP文庫) |
『大陸は動いている』
(竹内均 『大地 国語 五下』 光村図書) |
『ウェゲナーの大陸移動説は仮説実験の勝利』
(西村敏雄 文芸社) |
『大陸と海洋の起源』
(アルフレッド・ウェゲナー 竹内均訳 講談社) |
『新科学哲学』
(板倉聖宣 仮説社) |
『第三世代の学問 「地球学」の提唱』
(竹内均、上山春平 中公新書) |
『アブダクション 仮説と発見の論理』
(米森裕治 勁草書房) |
『科学・モデル・アナロジー』
(M.ヘッセ/高田紀代志訳 培風館) |
◎
| 言葉のみならず、4回も改訂なされた事実から、ウェゲナー氏の迫力、意気込みが伝わってきます。 |
→
| ウェゲナーの言葉からのみならず、4回も改訂なされた事実から、ウェゲナーの情熱&意気込みが伝わってきます。 |
◎ 一方で、ダーウィンの『種の起原』をじかに読むべきだと思いました。
→ 一方で、ダーウィンの『種の起原』をじかに読むべきだと思うに至りました。
◎最初にインパクトがあったのは、ダーウィン氏自身が、実際に“生存闘争”なる言葉を紡いでいたことがわかる次の部分です。(巻頭の訳者まえがき→巻末の「解題」にて)
→ 最初にインパクトがあったのは、次の部分です(巻頭の訳者まえがき→巻末の「解題」にて)。
◎ 確かに、自然界には、競争の面── 例えば、“(太陽光、食糧等の)恵みの受け取り競争、(メスを獲得するための)オス同士の競い合い…”の面があると思います。
→ 確かに、自然界には、競争の面── 例えば、“(太陽光、食糧等の)恵みの受け取り競争、(メスを獲得するための)オス同士の競い合い…”の面があります。
◎ ダーウィンの『種の起原』の比喩(言葉使い)が、偏っているだけではありませんでした。
→ ダーウィンの『種の起原』は、比喩(言葉使い)が偏っているだけではありませんでした。
◎※新しいレベルの創発をともなう“大きな進化”の具体例には、『生体高分子社会(∋原核細胞)→真核細胞』『細胞→細胞社会』『細胞社会→個体(多様な細胞社会の調和体)』『人間→人間社会』『個体社会→生態系』… が挙げられます。
これらは、いがれも、3ステップス理論(3Steps Theory)の各レベルの創発に相当しています。
→※新しいレベルの創発をともなう“大きな進化”の具体例には、『生体高分子社会(∋原核細胞)→真核細胞』『細胞→細胞社会』『細胞社会→個体(多様な細胞社会たちの調和体)』『人間→人間社会』『個体社会→生態系』… が挙げられるのでした。
これらは、いずれも、3ステップス哲学の各レベルの創発に相当しています。
◎ したがって、『Against』のみを重視していることは、必然的に、ダーウィンの『種の起原』が、生態系の崩壊を含む“大きな退化”を扱ってしまっていることを意味しているのです。
→ したがって、『Against』のみを重視していることは、必然的に、ダーウィンの『種の起原』が、生態系における“大きな進化”を扱えないことを意味しているのです。
◎引用部の一部削除あり
◎該当部分 人生レベル→人間レベル
◎※生態系レベルの3ステップスも、本来、新たなレベルとして創発して生まれてきた“大きな進化”の所産です。
生態系レベルの3ステップスは、『For』が『Against』を上回れば、繁栄・存続し、逆に下回れば、衰退・絶滅するという“法則”に匹敵しています。
→※生態系レベルの3ステップスも、本来、新たなレベルとして創発して生まれた“大きな進化”の所産です。
生態系レベルの3ステップスは、『For』が『Against』を上回れば、繁栄・存続し、逆に下回れば、衰退・絶滅するという“法則”に相当しています。
◎ したがって、『Against』のみを重視していることは、必然的に、ダーウィンの『種の起原』が、生態系における“大きな進化”を扱えないことを意味しているのです。
→ したがって、『Against』のみを重視していることは、必然的に、ダーウィンの『種の起原』が、生態系における“大きな進化”を扱えていないことを意味しているのです。
◎追加
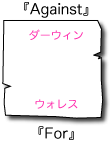
◎追加 ※この『For』の与え合い(恵み・フルーツの与えあい、シナジー、協調(調和)…)の関係の構築が存続につながることを、やはり、「『Love‐Loveの関係』を構築する存在こそが存続できること」が意味しています。
◎ 筆者は、人間の『精神的な特性』や『人間の道徳的および知的な性質』は、本来、高度な言語の使用が前提となる“人間レベル、人間社会レベルによって育まれたのだと考えます。
→ 人間の『精神的な特性』や『人間の道徳的および知的な性質』は、本来、高度な言語の使用が前提となる“人間レベル、人間社会レベルによって育まれたのだと筆者は考えます。
◎追加
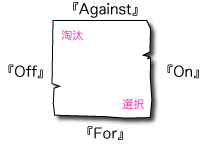
◎ ダーウィンやウォレスは、本来は、純粋に自然科学をしていたかったのだと思います。
→ ダーウィンやウォレスは、本来は、純粋に健全な自然科学──「自然(nature)と調和を探究する営み」としての自然科学をしていたかったのだと思います。
◎ダーウィンやウォレスが、純粋に自然科学をしていたかったという考えを支持しています。
→ ダーウィンやウォレスが、純粋に健全な自然科学──「自然(nature)と調和を探究する営み」としての自然科学をしていたかったという考えを支持しています。
◎ ダーウィンやウォレスは、博物学における厳密(科学的)な法則を打ち立てるべく、本来、自然(nature)との調和を探究していたのです。→ ダーウィンやウォレスは、本来、博物学における厳密(科学的)な法則を打ち立てるべく、ひたすら自然(nature)との調和を探究する営みとしての自然科学していたのです。
◎削除 ※『ダーウィンの法則』(『宇宙に法則はあるのか』 ジョン・D・バロウ著 松浦俊輔訳 青土社 p.117-118)には、『ダーウィンの法則』の本質がNatural Selection〈自然淘汰&自然選択〉であることが示されています。しかも、そのNatural Selection〈自然淘汰&自然選択〉の起源が、ウィリアム・ウェルズ(アメリカの医師)による論文の発表(1813)であることが示されています。
医師の名はウィリアム・ウェルズといい論文は「皮膚の一部が黒人に似たある白人女性の話」という題だった。その論文でウェルズが説いたのは、生物に現に見られる身体的特徴の存在を説明するもので、今日われわれが自然淘汰と読んでいるものだった。ウェルズはその仮説を、人間の皮膚の色が気候に適応する事例研究から導いた。…品種改良という人為的な選択によって適応を実行できるのならば、この適応は、「自然によって、もっとゆっくりとではあっても、同じ効力で」達成しうるというのである。…ウェルズが当初無視された理由が何であれ、その名はいずれ、ダーウィンの『種の起原』の後の方の版に登場する。一八六〇年、このアメリカの無名の科学者による研究にダーウィンの目がやっと向けられ、自然淘汰という考え方の創始者として認められたのである。
ダーウィンとアルフレッド・ウォレスは、生物界に秩序が存在することの説明としての自然淘汰の仕組について、その証拠を収集するという点で、ウェルズよりはるかに先へ行っていた。…
(『宇宙に法則はあるのか』(ジョン・D・バロウ著 松浦俊輔訳 青土社 p.117〜118) 下線は筆者によります。 |
◎ ダーウィンやウォレスは、自然(nature)との調和を探究していたからこそ、(特に宗教的な批判を含む)さまざまな批判を浴びることが予想される考えを、あえて公にできたのだと考えられます。
→ ひたむきに自然(nature)との調和を探究していたからこそ、ダーウィンやウォレスは、(特に宗教的な批判を含む)さまざまな批判を浴びることが予想される考えを、あえて公にできたのです。
◎※批判を覚悟して公にしたことは、「天動説をとなえたコペルニクス」や「その天動説を(多くの証拠を示しながら)支持したガリレオ」も同様だったのだと思います。なお、ウェルズがコペルニクスの立場、(多くの証拠を示したので)ダーウィンやウォレスがガリレオの立場に近かったという見方も成立するかもしれません。
→※批判を覚悟しながら成果を公にしたことは、「天動説をとなえたコペルニクス」や「その天動説を(多くの証拠を示しながら)支持したガリレオ」も同様だったと思います。
※なお、『ダーウィンの法則』(『宇宙に法則はあるのか』 ジョン・D・バロウ著 松浦俊輔訳 青土社 p.117-118)では、『ダーウィンの法則』として、Natural Selection〈自然淘汰&自然選択〉が挙げられているのみならず、そのNatural Selection〈自然淘汰&自然選択〉の起源が、ウィリアム・ウェルズ(アメリカの医師)による論文の発表(1813)であることが示されています。
医師の名はウィリアム・ウェルズといい論文は「皮膚の一部が黒人に似たある白人女性の話」という題だった。その論文でウェルズが説いたのは、生物に現に見られる身体的特徴の存在を説明するもので、今日われわれが自然淘汰と読んでいるものだった。ウェルズはその仮説を、人間の皮膚の色が気候に適応する事例研究から導いた。…品種改良という人為的な選択によって適応を実行できるのならば、この適応は、「自然によって、もっとゆっくりとではあっても、同じ効力で」達成しうるというのである。…ウェルズが当初無視された理由が何であれ、その名はいずれ、ダーウィンの『種の起原』の後の方の版に登場する。一八六〇年、このアメリカの無名の科学者による研究にダーウィンの目がやっと向けられ、自然淘汰という考え方の創始者として認められたのである。
ダーウィンとアルフレッド・ウォレスは、生物界に秩序が存在することの説明としての自然淘汰の仕組について、その証拠を収集するという点で、ウェルズよりはるかに先へ行っていた。…
(『宇宙に法則はあるのか』(ジョン・D・バロウ著 松浦俊輔訳 青土社 p.117〜118) 下線は筆者によります。 |
ウェルズがコペルニクスの立場、(多くの証拠を示しましたので)ダーウィンやウォレスがガリレオの立場に近かったという見方も成立すると思います。
◎ このような『ダーウィンもウォレスも、ニュートンになりたかった』という記述がヒントとなり、重力(による多様な物質の生成)、生態系、「人生(心、感情、価値観、倫理、哲学…)、人間社会…」が互いに3ステップス的に相似であることをもとにして次の考えが導かれました。
→ このような『ダーウィンもウォレスも、ニュートンになりたかった』という記述がヒントとなり、万有引力の法則が働く系(重力によって多様な物質が生成する系)、Natural Selection〈自然淘汰&自然選択〉が働く系(生態系)、「人間(人生、心、感情、価値観、倫理、哲学…)、人間社会…」の系が互いに3ステップス的に相似であることをもとにして次の考えが導かれました。
◎「人生(心、感情、価値観、倫理、哲学…)、人間社会…」の生成過程も、立派な自然法則であるという考えを詳しく説明すると次のようになります。
→ 「人間(人生、心、感情、価値観、倫理、哲学…)、人間社会…」の生成過程も自然法則であるという考えを詳しく説明すると次のようになります。
◎該当部分 人生→人間
◎該当部分 細胞の社会レベル→細胞社会レベル
◎該当部分 機能性高分子の社会レベル→生体高分子社会レベル
◎該当部分 細胞の社会→細胞社会
◎該当部分 統合体→調和体
◎該当部分 “機能性高分子の社会”→生体高分子社会
◎該当部分 さまざまな→多様な
◎該当部分 “細胞社会”→細胞社会
◎該当部分 機能性高分子→生体高分子
◎該当部分 生体高分子の社会→生体高分子社会
◎該当部分 存続してきました。
→存続しました。
◎該当部分 個体の社会→個体社会
◎“個体社会”→個体社会
◎該当部分 “細胞社会”の調和体レベル→さまざまな細胞社会たちの調和体レベル
◎該当部分 人生(心、感情、価値観、倫理、哲学…)→人間(人生、心、感情、価値観、倫理、哲学…)
◎該当部分 調和(協調)体→調和体
◎該当部分 (=多様な人間社会の調和体)→(=多様な人間社会たちの調和体)
◎該当部分 (=人間社会の調和体レベル)→(=多様な人間社会たちの調和体レベル)
◎該当部分 (=多様な生体高分子社会の調和体)→ (=多様な生体高分子社会たちの調和体
◎該当部分(=多様な細胞社会の調和体)→(=多様な細胞社会たちの調和体)
◎該当部分 多様な人間社会→多様な人間社会たち
◎厳密には、(人類には観測できない)ごくごく小さな多様性がかくれているのです。
→厳密には、(人間には観測できない)ごくごく小さな多様性がかくれているのです。
◎この(ダーウィンやウォレスのNatural Selection(自然淘汰&自然選択)の法則にしたがう)生態系の生成過程は、ニュートンの万有引力の法則よりも、はるかに大きな多様性を持っています。(人間や人間社会や人類よりも、とても大きな多様性を持っています)
→ この(ダーウィンやウォレスのNatural Selection(自然淘汰&自然選択)の法則にしたがう)生態系の生成過程は、ニュートンの万有引力の法則よりも、はるかに大きな多様性を持っています(人間や人間社会や人類の生成過程よりも、とても大きな多様性を持っています)。
◎ すなわち、人間の(多様な)生成過程は、まさに、万有引力の法則やNatural Selection(自然淘汰&自然選択)の法則と同様なしくみによって生まれている決まった流れそのものだからです。
→ すなわち、人間の(多様な)生成過程は、まさに、万有引力の法則やNatural Selection(自然淘汰&自然選択)の法則と相似なしくみ(3ステップス)によって生まれている決まった流れそのものだからです。
◎ すなわち、人間社会の(多様な)生成過程は、まさに、万有引力の法則やNatural Selection(自然淘汰&自然選択)の法則と同様なしくみによって生まれている決まった流れそのものだからです。
→ すなわち、人間社会の(多様な)生成過程は、まさに、万有引力の法則やNatural Selection(自然淘汰&自然選択)の法則と相似なしくみ(3ステップス)によって生まれている決まった流れそのものだからです。
◎該当部分 “個体の社会”→“個体社会”
◎(人生や人間社会や人類よりも、とても大きな多様性を持っています)
→(人間や人間社会や人類よりも、とても大きな多様性を持っています)
◎※なお、(人間の生成過程の法則、人間社会の生成過程の法則と同様に)万有引力の法則は“多様な物質の生成過程の法則(の一例)”と呼べることになります。また、Natural Selection〈自然淘汰&自然選択〉の法則は、“生態系の生成過程の法則(一部)”と呼べることになります。
→※なお、万有引力の法則は“多様な物質の生成過程の法則(の一例)”です。また、Natural Selection〈自然淘汰&自然選択〉の法則は、“生態系の生成過程の法則(の一部)”です。
◎ ただし、やはり、自然科学は「霊」「霊魂」… を断固として却下し続けるべきです。したがって、「“「霊」そのもの”が、あらゆるレベルに存在している」という考え自体は、はっきり自然(nature)から乖離していると判断するべきです。
→ ただし、やはり、自然科学は「霊」「霊魂」… という人間の心の対象(想像内容)を自然(nature)から乖離していると判断し続けるべきです。「“「霊」そのもの”が、あらゆるレベルに存在している」という考え自体も、はっきり自然(nature)から乖離していると判断し続けるべきです。
◎ ダーウィンとウォレスの考えは、Natural Selection(自然淘汰&自然選択)の点では同じでしたが、心についての考えは、異なっていました。
ダーウィンは、心も体も、動物からの進化の延長上の所産として説明しました。ウォレスは、体については動物からの進化の延長上の所産として説明した一方で、心については、体への進化とは独立した人間独特の「霊」的なものだという考えを取りました。
自然科学は、やはり、「霊」「霊魂」… を断固として却下すべきです。
→ ダーウィンとウォレスの考えは、Natural Selection(自然淘汰&自然選択)の点では本質的に同じでしたが、Natural Selection〈自然淘汰&自然選択〉の解釈のみならず、心についての考えも異なっていました。ダーウィンは、心も体も、動物からの進化の延長上の所産として説明しました。ウォレスは、体については動物からの進化の延長上の所産として説明した一方で、心については、体への進化とは独立した人間独特の「霊」的なものだという考えを取りました。心についての考えについては、ダーウィンの方が自然(nature)と調和しており、ウォレスの方が自然(nature)から乖離していると思います)
→
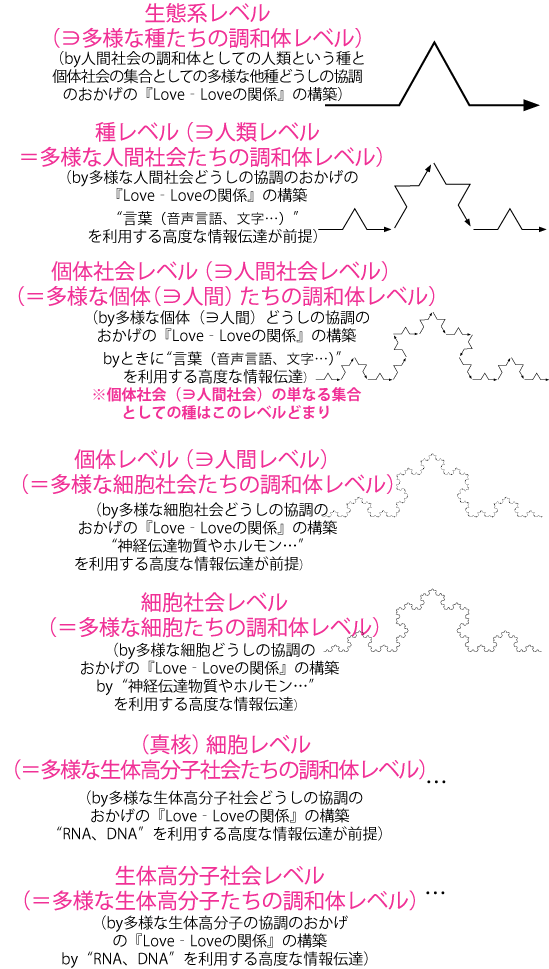 |
◎自然法則にしたがいながら進化してきた一面も持ち続けています。
→自然法則に従いながら進化してきた一面も持ち続けています。
◎への進化です。
への成熟にもとづきます。
◎高い目的意識を持ってソフトウェアの未熟な部分を成熟したものへと積極的(能動的)に書き変えるという選択によって有目的な進化を実現していくことができるのです。
→高い目的意識を持ってソフトウェアの未熟な部分を成熟したものへと積極的(能動的)に書き変えるという選択によって有目的な進化を実現することができるのです。
◎ すなわち、何十億年(少なくとも30億年)の出来事(史実)を生んできたのは、「(空間的にも時間的にも)広い協調(調和)」路線にもとづく、さまざまなレベルの自然法則、生成過程の法則でした。
→ すなわち、何十億年(少なくとも30億年)の出来事(史実)を支え続けたのは、「(空間的にも時間的にも)広い協調(調和)」路線にもとづく、さまざまなレベルの自然法則、生成過程の法則でした。
◎ 生成過程の法則という自然法則によって生み出されてきた何十億年(少なくとも30億年)の出来事(史実)の例を詳しく挙げると次のようになります。
→ 生成過程の法則という自然法則によって支えられ続けた何十億年(少なくとも30億年)の出来事(史実)の例を詳しく挙げると次のようになります。
◎該当部分 生み→支え
◎「核子やレプトン→「核子やレプトンたち
◎多様な物質はこれまで存続しました。→これまで存続する多様な物質を生成し続けました。
◎「多様な物質から→「多様な物質たちから
◎生体高分子はこれまで存続しました。
→これまで存続する生体高分子を生成し続けました。
◎「多様な生体高分子から→「多様な生体高分子たちから
◎生体高分子社会(原核生物〈細菌&古細菌〉…)はこれまで30億年以上の間(多様な形で)存続しました。
→これまで30億年以上の間(多様な形で)存続する生体高分子社会(原核生物〈細菌&古細菌〉…)を生成し続けました。
◎「多様な生体高分子社会(原核生物〈細菌&古細菌〉…)から→「多様な生体高分子社会(原核生物〈細菌&古細菌〉…)たちから
◎真核細胞はこれまで20億年以上の間(多様な形で)存続しました。
→これまで20億年以上の間(多様な形で)存続する真核細胞を生成し続けました。
◎「多様な細胞(真核細胞)から→「多様な細胞(真核細胞)たちから
◎細胞社会(単純な多細胞生物…)はこれまで10億年以上の間(多様な形で)存続しました。
→これまで10億年以上の間(多様な形で)存続する細胞社会(単純な多細胞生物…)を生成し続けました。
◎「多様な細胞社会(単純な多細胞生物…)から→「多様な細胞社会(単純な多細胞生物…)たちから
◎眼を持つような複雑な個体はこれまで5億年以上の間(多様な形で)存続しました。
→これまで5億年以上の間(多様な形で)存続する眼を持つような複雑な個体を生成し続けました。
◎それぞれの個体から、→それぞれの個体たちから
◎個体社会はこれまで(多様な形で)存続しました。
→◎ なお、個体から個体社会へと至る大きな進化には、多様な人間から人間社会へ至る進化も含まれます。
→ なお、個体たちから個体社会へと至る大きな進化には、多様な人間たちから人間社会へ至る進化も含まれます。
◎「多様な個体社会から、
→「多様な個体社会たちから
◎生態系はこれまで(多様な形で)存続しました。
→これまで(多様な形で)存続する生態系を生成し続けました。
◎該当部分で追加 たち
◎ ※何十億年(少なくとも30億年)の間に起きた出来事(史実)を生んできた生成過程の法則という自然法則を、単純に整理すると次のようになります。
→※生成過程の法則という自然法則を、単純に整理すると次のようになります。
人類の生成の法則以外は、何十億年(少なくとも30億年)の間に起きた出来事(史実)です。
◎テーブルに色をつける。
|