このように、筆者はアドラーの共同体感覚によって励まされているのみならず、アドラーの共同体感覚を支持しています。
ここにシナジー関係が成立していると思います。
アドラーの存在に、筆者は励まされております。
アドラーの存在に気づかせてくださった、アドラーブームにも感謝しております。
アドラーの偉大さは、決してゆらぎません。
しかし、一方で、筆者は、例によって、アドラーのすべてを鵜呑みにし、すべてにおいて同調しているわけではありません。(そのようなことをしたら、やはり自分をなくしてしまうと思います)
ところどころ“違い”があることに気づいています。
例えば、先の引用の前部に“違い”を感じました。
…生後数ヶ月で既に、子どもが、その後の人生でどんなふうにふるまうかがわかる。それ以後は、二人の乳児を人生への態度に関して取り違えることは、もはや不可能である。なぜなら、誰もがはっきりと刻まれたタイプを表し、それは、いよいよはっきりとし、一度与えられた方向を見失うことはないのである。
子どもの心の発達は、子どもをめぐる対人関係によって、ますます浸透される。生得的な共同体感覚の最初の兆候が現れ、器官に制約された愛情追求が盛んになり、子どもは大人が近くにいることを求めるまでになる。子どもの愛情追求は、フロイトがいうように、自分自身にではなく、他の人に向けられることが常に見られる。これは子どもによって現れ方も異なる。二歳以上の子どもでは、この違いは、言葉の表現にも確かめることができる。この頃までにしっかりと根づいた、[共同体との]一体感、共同体感覚は、精神がひどく病んだ時だけに失われる。それを人は制限されたり、あるいは、拡大されて、少し色合いを変え、形を少しばかり変えることはあっても、生涯にわたって持ち続け、良好な状態の時には、家族だけではなく、一族、国家、全人類にまで拡大する。さらには、この限界を超え、動物、植物や無生物まで、ついには、宇宙にまで広がる。われわれは、人間を理解するために重要な助けを手に入れた。人間を共同体的存在として見なければならないのである。
(p.49〜50『人間知の心理学』 アルフレッド・アドラー 岸見一郎訳 アルテ) 下線は筆者によります。 |
“はぎれのよい断定調”で示された『後数ヶ月で既に、子どもが、その後の人生でどんなふうにふるまうかがわかる。それ以後は、二人の乳児を人生への態度に関して取り違えることは、もはや不可能である。なぜなら、誰もがはっきりと刻まれたタイプを表し、それは、いよいよはっきりとし、一度与えられた方向を見失うことはないのである。』という言葉に、筆者は、“違い”を感じます。
確かに、ときには、生後数ヶ月、乳児、二歳で、人生が決まってしまう場合もあるかもしれません。しかし、一方で、生後数ヶ月、乳児、二歳で、人生が決まらない場合もあると思います。
少なくとも筆者は、生まれや育ちに関係なく、大人になってからでも、何歳になってからでも、共同体感覚、および、For All Life(=For『In』& For『Out』)路線を育めると思います。
たとえ(恵まれていなかった)小さい頃や(ストレスフルな状況で)心を病んでいたときを含めて、わがままで自分のことばかり考えていた醜い時代があったとしても、それでも、コツコツ努力して、共同体感覚、For All Life(=For『In』& For『Out』)路線を育めると思います。
人間には、もっともっと可能性がつまっていると思います。
人間には、何歳からでも成長&成熟できる可能性がつまっていると思います。
人間には、より美しく花を咲かせられる可能性がつまっていると思います。
人間には、自己実現を達成する可能性がつまっていると思います。
…
※以上の文章をすでにまとめ終わっていたのちに、次の記述に出会いました。
共同体感覚は生まれつきのものではない。
誰もが皆、平等にその種を持って生まれてきている。
親や教師は種に水をやり、太陽に当てなければならない。
(59 『アルフレッド・アドラー 一瞬で自分が変わる100の言葉』 小倉宏 ダイヤモンド社) |
筆者は、この記述内容に大変共感します。ただし、先の引用部の“前部”と矛盾しているようです。
アドラー自身が、のちに考えを変えた(改めた)のかもしれません。あるいは、小倉宏氏も“筆者と同様な違和感”を持ったがゆえに、59の言葉を紡いで、アドラーをフォローしてくださったのかもしれません。あるいは、アドラー自身の説とアドラーの後継者の説が微妙に異なっているのかもしれません。実際どうなのか今の筆者にはわかりません。
いずれにせよ、小倉宏氏の次の言葉に筆者はとても共感しております。
もしかしたら、アドラーに抱く“違和感”のいくつかは、もしかしたら、アドラーの意図、主旨… を十分に把握していないからに過ぎないのかもしれないとも思います。
しかし、いずれにせよ、どちらかと言えば、アドラーの人生が『Against』の方向にあったとすれば、マズローの人生は『For』の方向にあったようです。
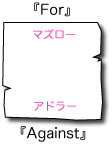
確かに、共同体感覚それ自体は、『For』の方向にあります。
しかし、劣等感、怒り、嫌われる、課題の分離、『精神がひどく病んだ時』、『〜してはいけない』『〜してはならない』、『〜なければならない』… は『Against』の方向にあります。
※なお、アドラーにとっての共同体感覚は、目標として設定されているもので、『良好な状態の時』にはじめて十分に達成されるものだったのに対して(『精神がひどく病んだ時』には失われるものだったのに対して)、マズローにとっての(人類に対する)共同体感覚は、自己実現的人間の特徴であり、前提でした(下記にそのことがわかる部分を引用してあります)。
アドラーは、『Against』の方向に注目し続け(=『Against』の方向から目をそらさずに)、心理学を育んでいたのだと思います。
それに対し、マズローは、『For』の方向にこそ注目して(=『For』の方向から目をそらさずに)、心理学を育んでいたのだと思います。
アドラーは、例外的に『良好な状態』のとき(健康なとき)についての心理もあつかいながらも、主に『悪い状態』のとき(病んでいるとき)についての心理をあつかっていたのだと思います。
それに対して、マズローは、例外的に『悪い状態』のとき(病んでいるとき)についての心理もあつかいながらも、主に『良好な状態』のとき(健康なとき)についての心理をあつかっていたのだと思います。
どちらかと言えば、アドラーが、主に『悪い状態』(病んでいる状態、くるしい状態、水中でおぼれている状態、非常事態、消極性・ネガティブさに惹かれる状態…)を脱するための心理学に取り組んでいたのに対し、マズローは、主に『よい状態』(健康な状態、ここちいい状態、陸地にあがっている状態、健常状態、積極性・ポジティブさに惹かれる状態…)を育むための心理学に取り組んでいたのだと思います。
つまり、どちらかと言えば、アドラーの心理学が「主に病まないための心理学」だとすれば、マズローの心理学は「主に、より健やかに生きるための心理学」だと要約できると思います。
※どちらかと言えば、アドラーが主に『Against』↓を目指していたとするなら、マズローは主に『For』↑を目指していたとも要約できます。その意味でも、やはり、どちらかと言えば、アドラーが『Against』の方向にいたとすれば、マズローは『For』の方向にいたことになります。
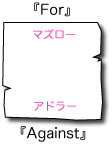
むろん、アドラー心理学には、アドラー心理学の存在意義が今後ともあり続けます。
ただし、アドラー心理学だけにとどまるよりも“アドラー心理学もマズロー心理学も”の方が、よりフルーツフルであると思います。
すなわち、アドラー心理学のみならず、アドラー心理学が源流となった(アドラー心理学に刺激を受けて育まれた)「人間性心理学」も合わせて学ぶことが、よりフルーツフルなのだと思います。
※なお、単純に、『悪い状態』のとき(病んでいるとき、くるしいとき、水中でおぼれているとき、非常事態のとき、消極性・ネガティブさに惹かれるとき…)には、アドラーとの相性がよくなり(アドラーへの共感度が高まり)、『よい状態』のとき(健康なとき、ここちいいとき、陸地にあがっているとき、健常状態のとき、積極性・ポジティブさに惹かれるとき…)には、マズローとの相性がよくなる(マズローへの共感度が高まる)とは限らないと思います。
なぜなら、『悪い状態』のとき(病んでいるとき、くるしいとき、水中でおぼれているとき、非常事態のとき、消極性・ネガティブさに惹かれるとき…)に、『よい状態』(健康な状態、ここちいい状態、陸地にあがっている状態、健常状態、積極性・ポジティブさに惹かれる状態…)をダイレクトに目指す人生もありうるからです。
悲しまないように生きるか。楽しむように生きるか。
不快さ・心地悪さを減らすように生きるか。快感さ・心地よさを増やすように生きるか。
病まないように生きるか。健康になるように生きるか。
…
『Against』の対極を目指すか、『For』をダイレクトに目指すか。
これらは、一見紙一重のようですが、大きな違いがあります。
注目している対象が違っているからです。
心的なエネルギー源が違っているからです。
一方は、恐れ、憎悪、不快さ、心地悪さ、悲しみ… を含む『Against』の方向のエネルギー源を利用していて、もう一方は、楽しみ、愛情、快感さ、心地よさ、悦び… を含む『For』の方向のエネルギー源を利用しています。
このあたりも、単純に相性があるだけでなく、状況に応じながら両方を大事にすることがフルーツフルなのだろうと思います。
とにもかくにも、アドラーブームは、筆者が心理学への関心を取り戻すきっかけとなりました。
さまざまなアドラー本を読めば読むほど筆者は刺激され、心理学への関心を再び深めました。
そして、同時に、マズローへの想いも再び深まったのでした。
人間の健全な可能性を探究していたマズロー──。
「人間がどこまで健全に成長(成熟)していけるか」を探究していたマズロー──。
自己実現的人間の特徴を調べていたマズロー──。
「人間性心理学」の確立に大きく貢献したマズロー──。
マズローを読みたい。
マズローを読むべきだ。
アドラーを読めば読むほど、「(学生時代にかじっていた)マズローを本格的に読みたい。よりじっくり読むべきだ」という想いが、ますます募ったのでした。
つまり、心理学とマズロー本との再会を強く促したのは、アドラー本だったのです。
マズロー本──『マズローの心理学』や『人間性の心理学』を本格的に読む際に、最初に特に惹かれた部分は、「心理学の系統(全体像)を示す部分」および「アドラーとマズローの関係がわかる部分」でした。

